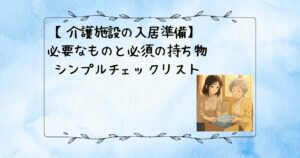1. はじめに:介護施設の入居準備、何から始める?
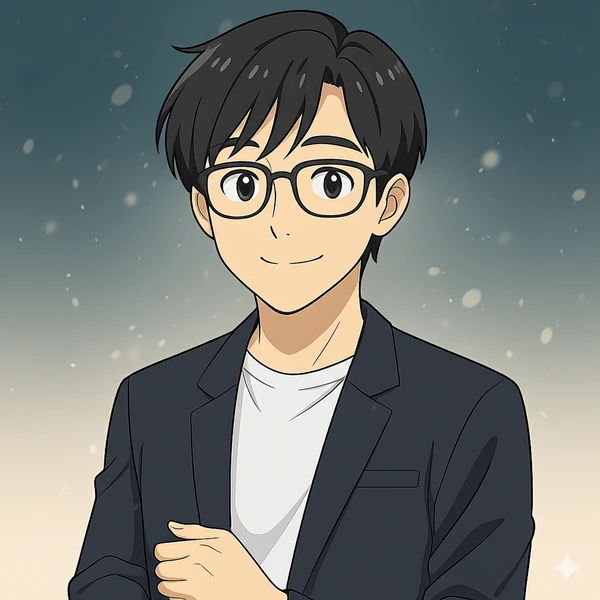
こんにちは!
元ITエンジニアで、現役介護福祉士のやなぎです。
皆さんはご家族が介護施設に入居する際に必要なものって何だと思いますか?
いざ準備を始めようと思っても、「一体、何から手をつければいいの?」「リストは見たけど、本当に全部必要なの?」と、戸惑うことも多いのではないでしょうか。
その不安な気持ち、とてもよく分かります。
この記事では、そうした不安を少しでも減らせるように、「これだけは準備しておきたい」という必須アイテムを中心に、シンプルで分かりやすいチェックリストを作成しました。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 何から準備すれば良いかが分かる
- 本当に必要な持ち物だけが分かる
- 準備の全体像がつかめ、不安が軽くなる
一緒に一つずつ確認していきましょうね!
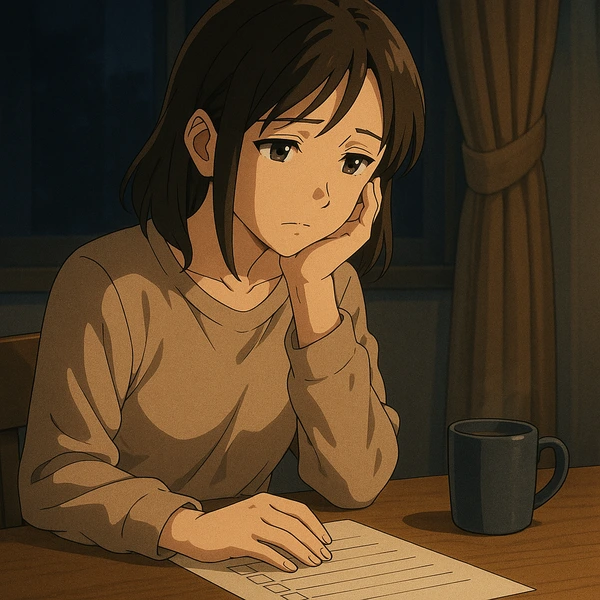
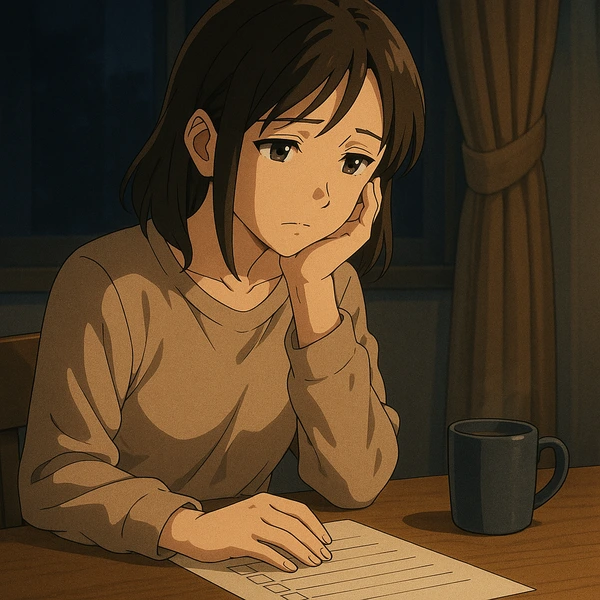
2. 準備をスムーズに進めるための「最初の3ステップ」
本題に入る前に、一番大切なことをお伝えしますね。
それは、「最初から完璧に全てを揃える必要はない」ということです。
いきなり細かい持ち物リストを見ると、かえって混乱してしまいますよね。
失敗しないコツは、まず全体の流れを掴むことです。
ここでは、準備をスムーズに進めるための「最初の3ステップ」をご紹介します。
- ステップ1:まずは施設からの「公式リスト」を確認
- 何よりも先に、入居する施設が用意している持ち物リストを取り寄せましょう。
これが一番正確な情報源です。同時に、持ち込みが禁止されているもの(例:電気ポット、延長コードなど)も確認しておくと、無駄な買い物を防げますよ。
特に施設によって備え付けてあるものや費用に含まれているものもありますので、気になることは取り寄せる際に聞いておきましょうね。
- 何よりも先に、入居する施設が用意している持ち物リストを取り寄せましょう。
- ステップ2:「安全」と「健康」に関わるものを最優先で考える
- 次に、リストの中からご本人の安全と健康に直結するものを優先的に準備しましょう。
例えば、「滑りにくい室内履き」「普段飲んでいるお薬」「お薬手帳」などです。
ここを最初に押さえておけば、気持ちに余裕が生まれますよ。
ご本人が普段愛用している杖や眼鏡、入れ歯など身に着けるものは忘れずに用意してあげてくださいね。
- 次に、リストの中からご本人の安全と健康に直結するものを優先的に準備しましょう。
- ステップ3:「その人らしさ」を保つアイテムを選ぶ
- 必需品の見通しが立ったら、最後に、新しい環境でもご本人が安心して過ごせるようなアイテムを選びましょう。「使い慣れた枕やひざ掛け」「ご家族の写真」「好きな本」など、その人らしさが感じられるものがあると、心の支えになります。
結構現場でお見かけするのが、枕やひざ掛け、羽織ものはご本人のお気に入りがあることが多く施設で安心して過ごすのに大切だったりしますよ。
- 必需品の見通しが立ったら、最後に、新しい環境でもご本人が安心して過ごせるようなアイテムを選びましょう。「使い慣れた枕やひざ掛け」「ご家族の写真」「好きな本」など、その人らしさが感じられるものがあると、心の支えになります。
この3つのステップで考えれば、何から手をつければ良いかが見えてきて、落ち着いて準備を進められますよ。


3. 【カテゴリー別】入居準備チェックリスト
ここでは、具体的な持ち物を、
「①衣類」
「②洗面・整容・衛生用品」
「③居室での生活用品」
「④その他」
の4つのカテゴリーに分け、より詳しく解説します。
① 衣類
- 普段着(上下5〜7セット):
- 理由: 日中に普段着へ着替えることで生活にメリハリが生まれます。汚れることも想定し、1週間分あると安心です。前開きのシャツや、ウエストがゴムのズボンなど、着替えやすいものを選びましょう。
- 前開きのパジャマ(3〜4着):
- 理由: 就寝時や体調が優れない時に。洗濯の頻度を考え、少し多めに準備します。介助が必要な場合、前開きがご本人・スタッフ双方の負担を減らせます。
- 下着・肌着(7枚以上):
- 理由: 汚れることが最も多いアイテムなので、多めに準備すると安心です。1週間分+予備数枚を目安にしましょう。
- 靴下(7足以上):
- 理由: 転倒予防のため、「滑り止め付き」が必須です。こちらも多めに用意しましょう。
- 羽織るもの(カーディガン、ベストなど2〜3枚):
- 理由: 施設内は空調が効いていますが、人によって体感温度は様々です。簡単に体温調節ができる羽織るものは季節を問わず重宝します。
- 室内履き(1足+予備1足):
- 理由: 施設内での転倒は大きな事故に繋がります。かかとが覆われ、滑りにくい、履き慣れた靴を選びましょう。汚れたり壊れたりした時のために予備があると安心です。
以下に施設でよくオススメしている室内履きのリンクを貼っておきますね。ご参考にしてください。
- 理由: 施設内での転倒は大きな事故に繋がります。かかとが覆われ、滑りにくい、履き慣れた靴を選びましょう。汚れたり壊れたりした時のために予備があると安心です。
- 外履き(1足):
- 理由: 通院や散歩など、外出時に必要です。こちらも履き慣れていて、着脱しやすいものを選びましょう。
- 季節もの(コート、セーター、マフラーなど):
- 理由: 外出時に備え、季節に合った上着も準備しておきましょう。衣替えの際に家族が入れ替えるのが一般的です。
② 洗面・整容・衛生用品
- 口腔ケア用品(歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、入れ歯ケース・洗浄剤):
- 理由: お口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防に繋がる大切なケアです。使い慣れたもの一式を準備してください。
ストロー付きコップもよくどれがいいかわからないという質問をいただくので、ご参考にリンクを貼っておきますね。
- 理由: お口の中を清潔に保つことは、誤嚥性肺炎の予防に繋がる大切なケアです。使い慣れたもの一式を準備してください。
- 整容用品(くし・ブラシ、爪切り、ひげそり、保湿クリーム):
- 理由: 身だしなみを整えることは、その人らしさや尊厳を保つ上で大切です。高齢になると肌が乾燥しやすいため、保湿剤は特に役立ちます。
- タオル類(バスタオル3〜4枚、フェイスタオル7〜10枚):
- 理由: 入浴だけでなく、洗顔や食事、清拭など、何かと使う場面が多いです。洗濯ローテーションを考え、少し多めに準備しましょう。
- 防水シーツ(1〜2枚):
- 理由: 万が一の失禁に備え、マットレスを汚損から守ります。衛生的な環境を保ち、シーツ交換の負担を軽減できます。(※これは施設に用意されていることが多いので事前に必ず確認してくださいね。)
- ティッシュペーパー、ウェットティッシュ:
- 理由: 居室にあると何かと便利です。消費が早いので、補充はご家族にお願いすることが多いです。
- ビニール袋(数枚):
- 理由: 汚れた衣類を入れたり、ゴミをまとめたりするのに役立ちます。
③ 居室での生活用品
- 使い慣れた寝具(枕、ブランケット、タオルケットなど):
- 理由: 環境の変化は大きなストレスです。慣れ親しんだ寝具の匂いや肌触りは、心を落ち着かせ、安眠に繋がる効果があります。
- 写真立て・アルバム:
- 理由: ご家族の写真は、ご本人にとって何よりの元気の源であり、寂しさを和らげるお守りになります。
- カレンダー・時計:
- 理由: 日付や時間が分かることは、生活リズムを整え、見当識(時間や場所の感覚)を保つ助けになります。文字盤が大きいものがおすすめです。
- 小さなゴミ箱、整理・収納ケース:
- 理由: 備え付けの棚やタンスを使いやすく整理するために役立ちます。中身が見える透明なケースが便利です。(※持ち込む際は、事前に施設へ確認しましょう)
- 趣味のもの(本、編み物、ラジオ、好きな音楽CDなど):
- 理由: 好きなことに取り組む時間は、新しい生活での生きがいになります。危険物でなければ持ち込み可能なことが多いです。
- クッション、ひざ掛け:
- 理由: 椅子や車椅子で過ごす時間も、お気に入りのクッションがあれば快適になります。ひざ掛けは足元の冷え対策に有効です。
- 割れない素材のコップ(湯呑み、マグカップ):
- 理由: 居室でお茶を飲む際などに使います。万が一落としても安全なように、プラスチックなどの割れない素材を選びましょう。
④ その他(必需品)
- お薬・お薬手帳:
- 理由: ご本人の命と健康に直結する最も重要なものです。数日分ではなく、現在服用しているものを全て、お薬手帳と一緒に持参しましょう。
- 杖・歩行器(本人に合ったもの):
- 理由: 体に合わない補助具はかえって危険です。普段から使っているもの、専門家が選んだものを必ず持参してください。
- 老眼鏡、補聴器(ケース、充電器、予備電池も):
- 理由: これらもご本人の生活の質に直結する必需品です。コミュニケーションや日々の楽しみに欠かせません。備品も忘れずに。
- 名前つけグッズ(油性ペン、名前シール、アイロンラベルなど):
- 理由: 施設では衣類や小物の紛失が頻繁に起こります。全ての持ち物にフルネームで名前を書いていただくことで、ご本人の大切な財産を守ります。
- 洗濯ネット(3〜4枚):
- 理由: 靴下や下着など、細かい衣類が他の人の洗濯物と混ざってしまうのを防ぎます。衣類を傷みから守る役割もあります。
- 各種保険証・印鑑など:
- 理由: 手続きに必要な重要書類です。施設から指示されたものを忘れずに準備しましょう。(※原本は家族が保管し、施設にはコピーを渡す場合もあります)
- 現金(小銭):
- 理由: 施設内の自動販売機や売店で使う場合に。多額の現金は不要です。管理方法については施設と相談しましょう。
4. よくある質問(Q&A)
僕が準備を進める中でよく聞かれる質問にお答えしますね。
5. まとめ:入居準備の3つのポイント
最後に、入居準備という長い道のりを歩むあなたに、お守りとして持っていてほしい大切な心構えを3つにまとめました。
- 完璧を目指さない「ほどよい加減」が、一番の近道。
- 「あれもこれも」と焦る必要はありません。むしろ、入居後にご本人の様子を見ながら「これが必要だね」と一つずつ揃えていく方が無駄がなく、ご本人に合ったものを選べますよ。
まずは「公式リスト」と「安全に関わるもの」だけ押さえれば、100点満点です!
- 「あれもこれも」と焦る必要はありません。むしろ、入居後にご本人の様子を見ながら「これが必要だね」と一つずつ揃えていく方が無駄がなく、ご本人に合ったものを選べますよ。
- モノ選びに迷ったら「安全 > 心地よさ > 便利さ」の順番で考える。
- たくさんの介護グッズを前にすると、どれが良いか迷ってしまいますよね。
そんな時は、この順番を思い出してください。まずは転倒などのリスクを減らす「安全」が最優先です。
次に、肌触りや使い慣れたものでご本人が落ち着ける「心地よさ」。
便利な機能はその次です。この”ものさし”があれば、判断に迷いませんよ。
- たくさんの介護グッズを前にすると、どれが良いか迷ってしまいますよね。
- あなたは一人じゃありません。一番の相談相手は、私たち「現場のスタッフ」です。
- 準備で悩むのは、ご家族にとって当然のことです。
どうか一人で抱え込まず、どんな些細なことでも私たち施設のスタッフに声をかけてくださいね。
「こんなこと聞いていいのかな?」は禁句ですよ!
ご家族からの相談は、ご本人をより深く知るための貴重な情報。
私たちは、あなたと一緒にケアを作るチームの一員です。
入居者さんについての情報や環境はスタッフがご本人と信頼関係を築き、安全に楽しく過ごしてもらうためにとっても大切なのですから。
- 準備で悩むのは、ご家族にとって当然のことです。
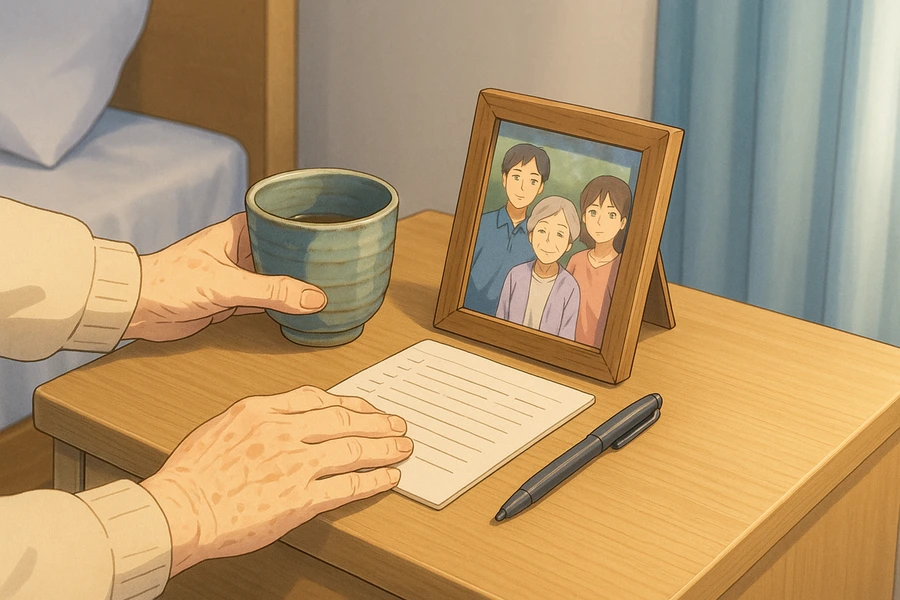
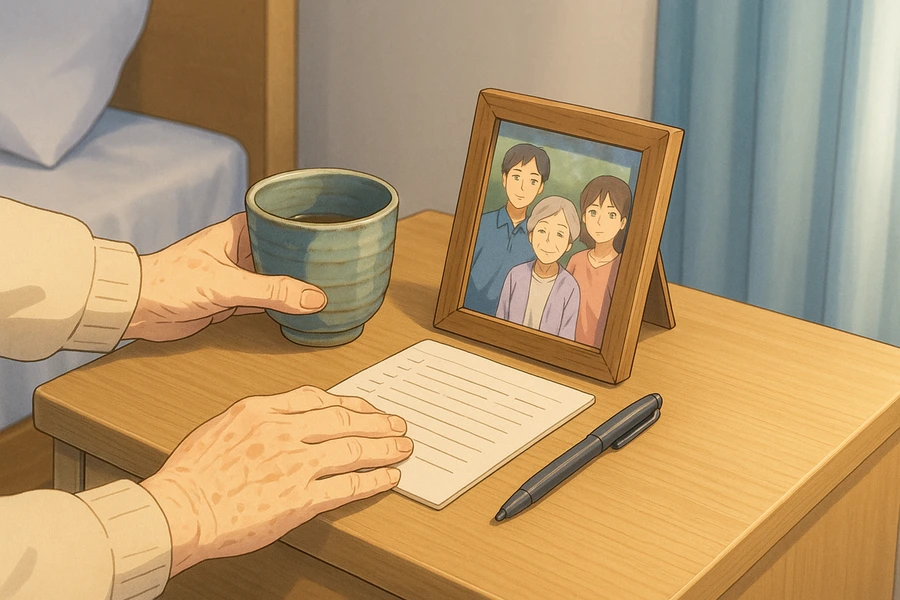
6. おわりに
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
そして、大切なご家族のために、ここまで準備を進めてこられたこと心からお疲れ様です。
たくさんの持ち物と向き合いながら、きっと、様々な想いが胸をよぎったことと思います。
でも、その一つひとつの準備が、これから始まる大切なご家族の新しい毎日を、そして、そこに笑顔で会いにいくあなた自身の未来を支える土台になっていきますよ。
どうか、一人ですべてを抱え込まないでくださいね。
私たちは、ご本人をケアするプロであると同時に、ご本人を支えるあなたの「一番の味方」でありたいといつも願っています。
もし、どうしても施設の人に聞けないけど気になることがある…なんて時は僕に相談いただいても大丈夫ですよ。
できる限りお力になりますからお問い合わせやSNSなどから遠慮なくご相談くださいね。
穏やかな気持ちで入居の日を迎えられますよう、心から願っています。


追伸:もう少しだけ、お付き合いください
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!
この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。
▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。
▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。
もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!




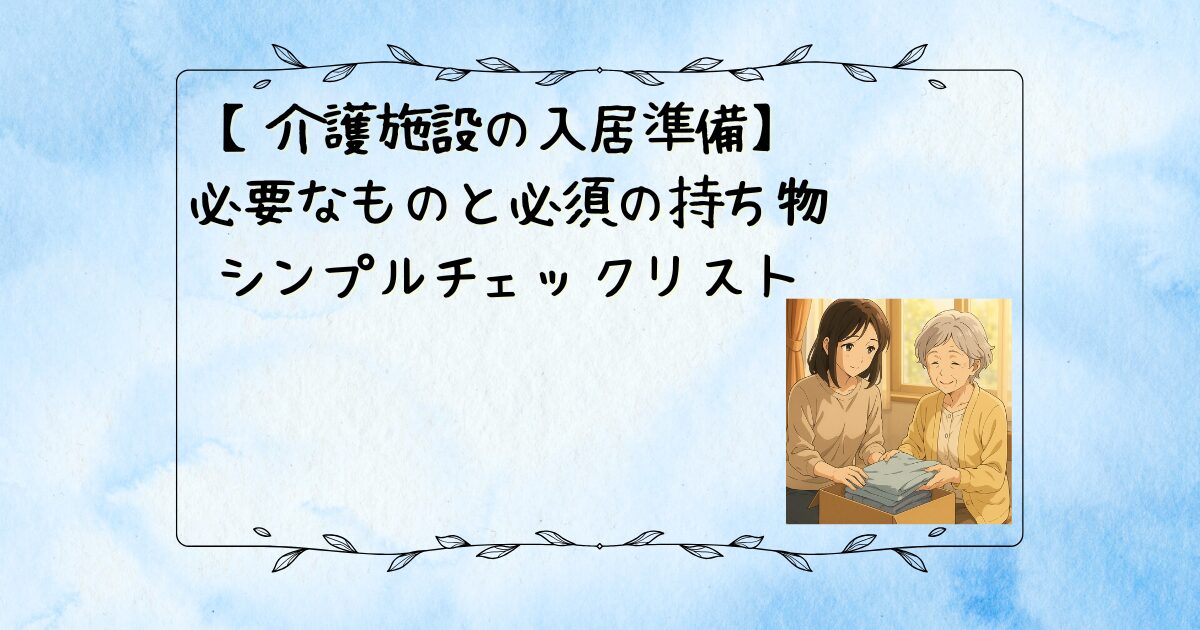
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c6d170c.5787b552.4c6d170d.3346c71a/?me_id=1220367&item_id=10000146&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fekaigoshop%2Fcabinet%2F24%2F933959-2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c6d26ae.1fda0913.4c6d26af.59568f01/?me_id=1267716&item_id=10000932&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftokutake%2Fcabinet%2Flabo%2F1097_doublemagic3%2F1097_main_03.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c6d170c.5787b552.4c6d170d.3346c71a/?me_id=1220367&item_id=10011608&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fekaigoshop%2Fcabinet%2F66%2F241666_3.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c6d5347.680b6978.4c6d5348.03c71877/?me_id=1309659&item_id=10150669&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcolorfulbox%2Fcabinet%2Fmaker_komori3%2F244077.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)