1. はじめに:もう記録と報告書に追われない!AIで「時間」を生み出す技術
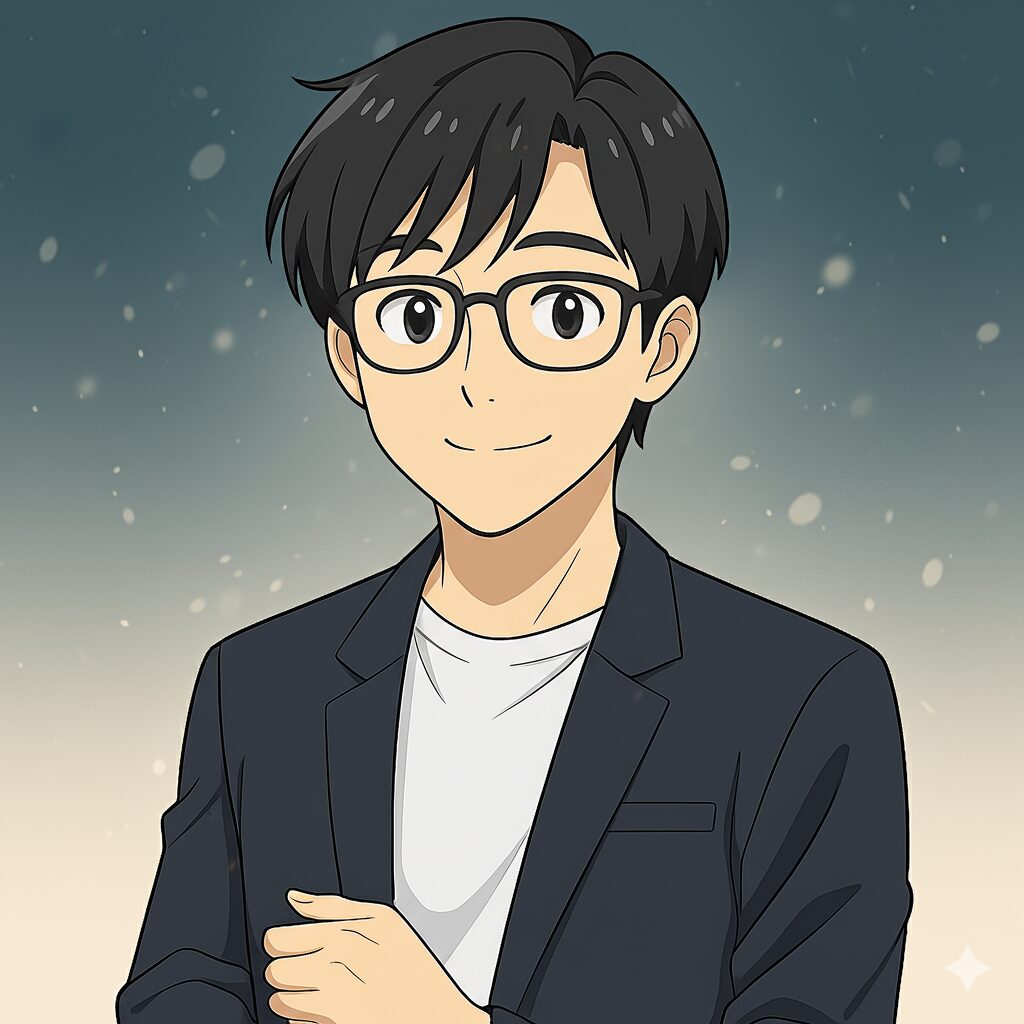
こんにちは!
介護福祉士で、特養で主任をしているやなぎと申します。
普段は介護現場の最前線で働きながら、空いた時間でExcelやAIツールを使って「どうすればもっと仕事が楽になるかな?」と考えるのが趣味、というちょっと変わった介護士です。
この記事を読んでくれているあなたも、きっと毎日こんな風に思っていませんか?
・「今日も記録が終わらない…日勤の残業は記録作業のため…」
・「カンファレンスの議事録、誰か代わりに書いてくれないかな…」
・「ヒヤリハット報告書、何から書けばいいか分からなくて手が止まる…」
めちゃくちゃ分かります。僕もずっとそうでしたから。
介護の仕事は好きだけど、正直、書類仕事だけは好きになれなかったんですよね。
でも、安心してください。
その悩み、今日で終わりかもしれません。
この記事では、最新の「生成AI」というテクノロジーを使って、あの面倒な書類仕事をあっという間に終わらせる具体的な方法を、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたにこんな変化があるはずです。
- 今まで1時間かかっていた書類仕事が、10分で終わるようになるかもしれない。
- 「何を書こう…」と白い紙の前で固まる時間がなくなり、質の高い文章がスラスラ書ける。
- そうして生まれた時間で、本当にやりたかったケア、利用者さんとじっくり向き合う時間に使える。
「AIなんて難しそう…」と感じる方も大丈夫です!
この記事で、登録から実践まで全部できるように書いたので、肩の力を抜いてゆっくりついてきてくださいね。
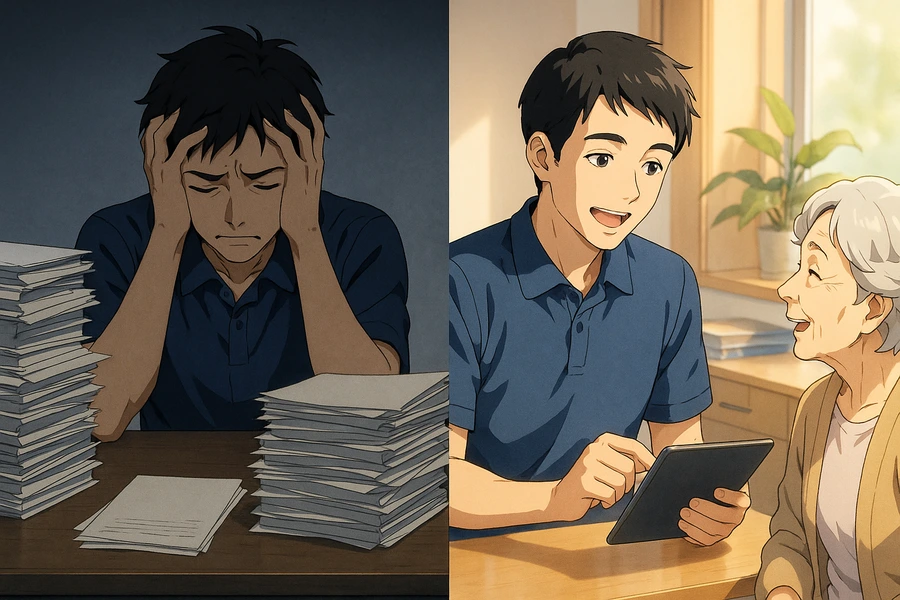
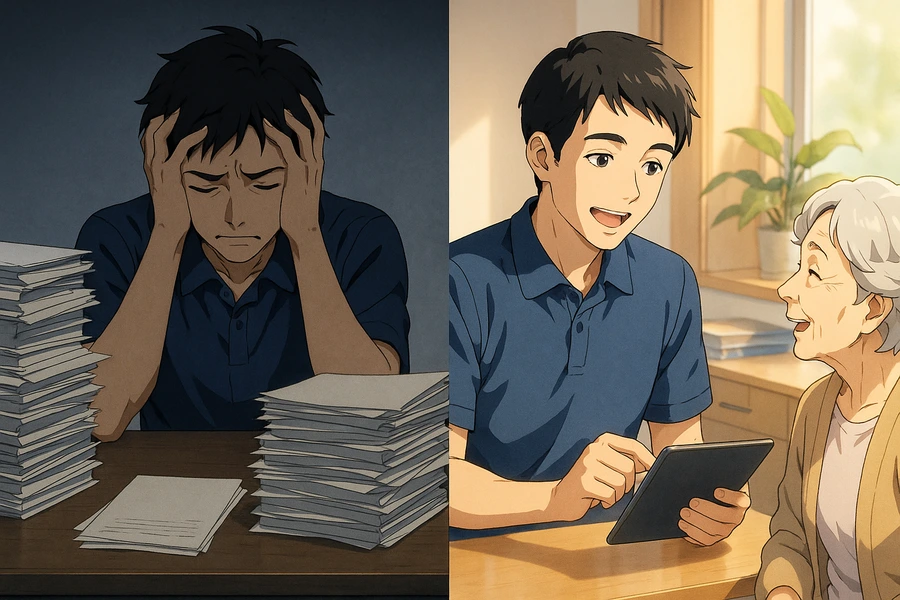
2. 結論:介護士はAIを「賢い部下」として育てて協力しよう
さっそく結論からお伝えしますね!
僕たち介護士は、「生成AI」を、まるで自分の部下のように協力していくのです。
正しく使えば、AIは少しの手間であなたの仕事量を劇的に減らしてくれる、最強の相棒になります。
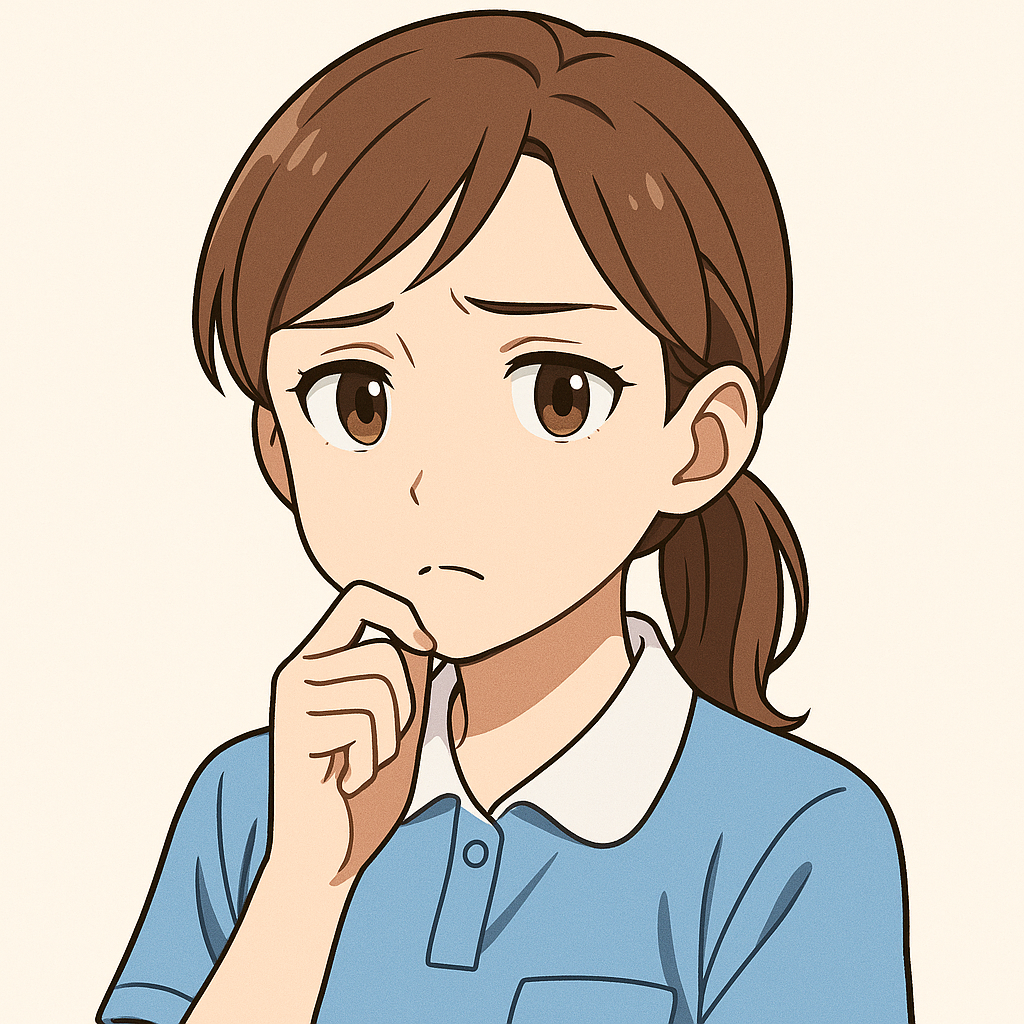
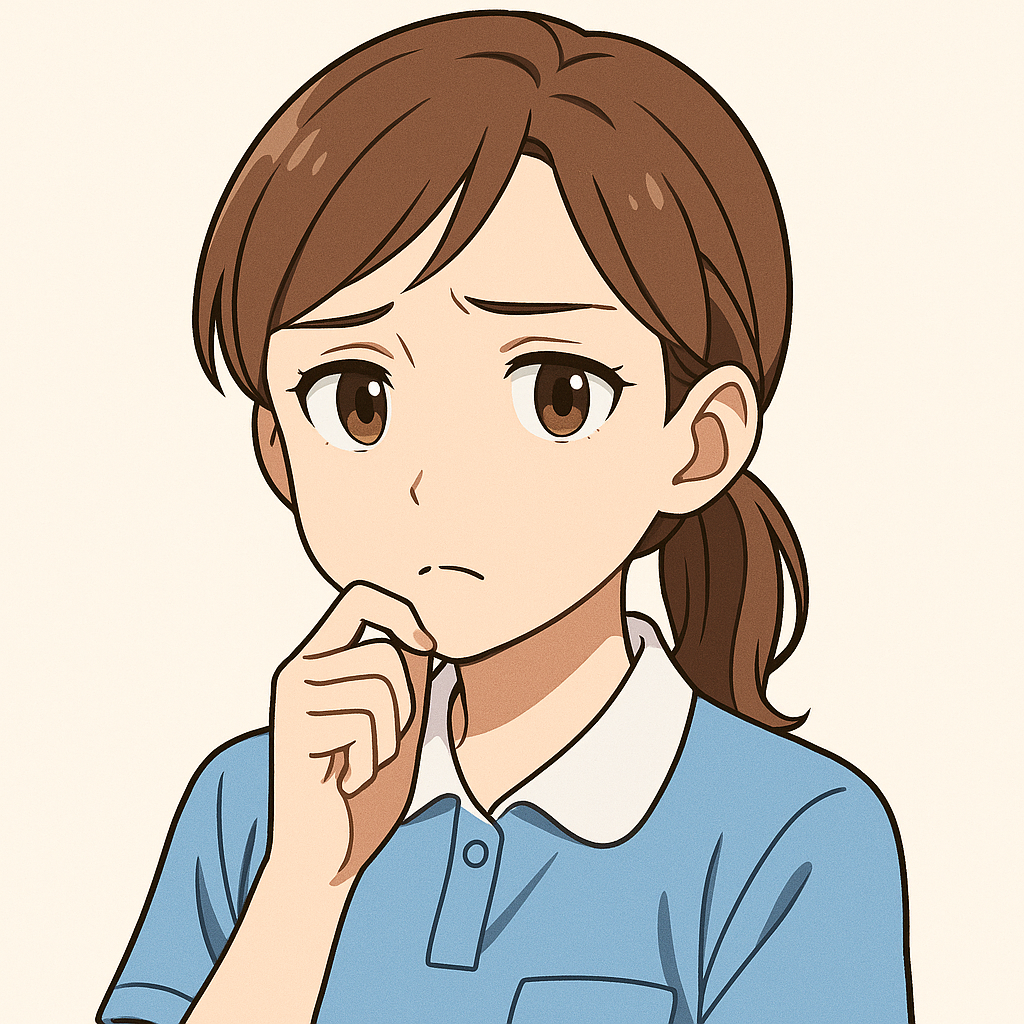
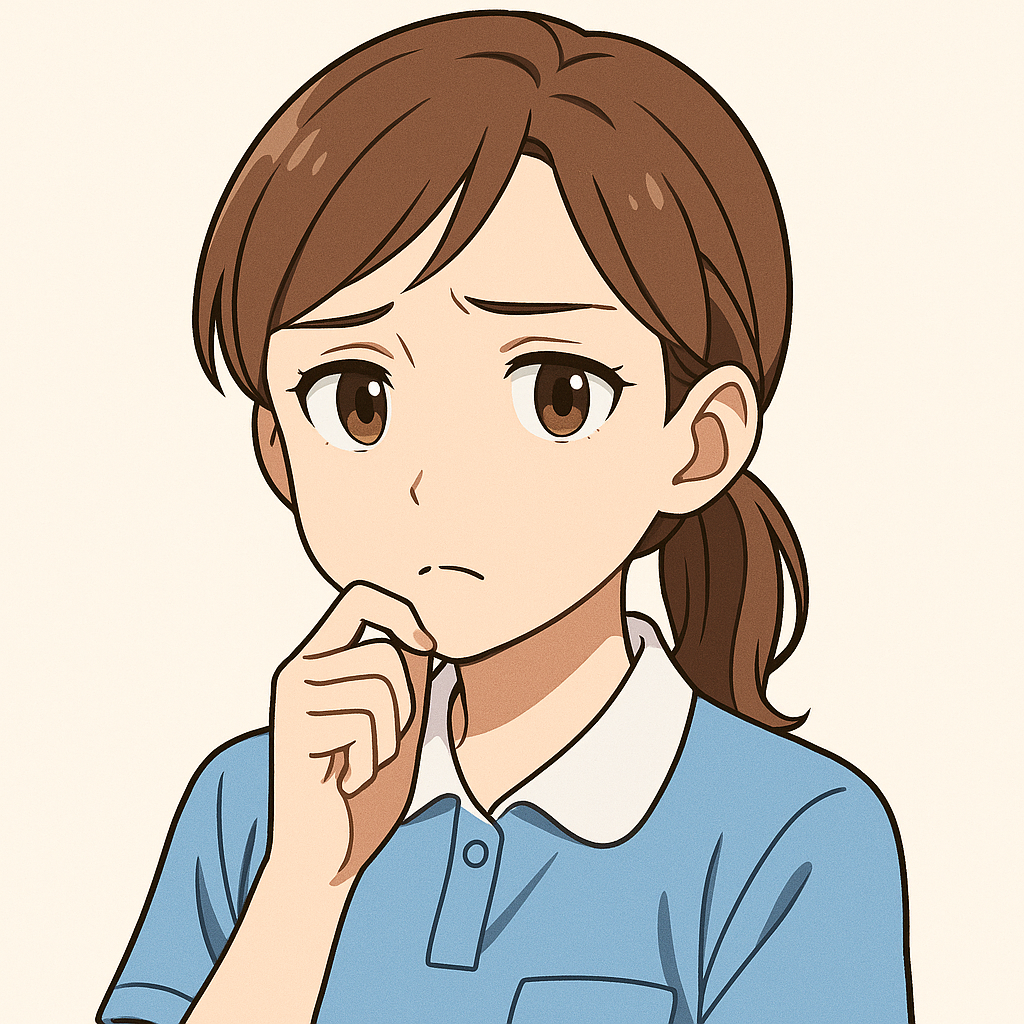
でも、無料だと大したことできないんでしょ?
いきなりお金がかかるのはちょっと…
初めから有料プランを使うのは抵抗があると思います。
でも大丈夫です、無料でも十分僕たちの力になってくれるので、安心してください。
「AIに仕事を奪われる!」なんて心配をたまに聞きますが、僕は全く逆だと思っています。
なぜなら、AIが得意なことって、実は❝私たち介護士が苦手だったり、時間を取られすぎていたりする部分❞だからです。
- 情報整理: バラバラの情報を、分かりやすく整理整頓する。
- 文章化: 箇条書きのメモから、きちんとした報告書の文章を作る。
- アイデア出し: レクリエーションの企画など、ゼロから1を生み出すヒントをくれる。
これって、まさに書類仕事の核心部分ですよね。
この部分をAIに任せられたら、どれだけ楽になるか想像してみてください。
ただし、とても大事なことが一つ。
AIは、まだ社会人1年目の新人部下のようなものです。
とても素直で能力は高いですが、指示が曖昧だとトンチンカンな答えを返してきたり、時々知ったかぶりして嘘をついたり(ハルシネーションと言います)することもあります。
そして、この新人部下に絶対に教えてはいけない、社会のルールがあります。
それが「個人情報」の取り扱いです。
会社の機密情報をペラペラ外部に話すようなことは、絶対にあってはいけませんよね。
この記事では、この「賢くてちょっとおっちょこちょいな新人部下(AI)」を、あなたの最強のパートナーに育てるための「的確な指示の出し方=プロンプト」を、余すところなくお伝えします。
この記事を読み終わる頃には、あなたもこの賢い部下を完璧に使いこなす「名指導者」になれますよ。
3.なぜ今、あなたの現場でAI活用が必須なのか?
3-1. 書類業務という名のラスボス
介護現場で働く私たちが、日々の業務で最後に戦うことになるラスボス…
それは間違いなく「書類業務」じゃないでしょうか。
介護記録、ケアプラン、各種報告書、カンファレンスの議事録などなど…
日中のケアとイレギュラーな業務でヘトヘトになった体…
最後の力を振り絞って記録と向き合う時間…
この時間が、私たちのHP(体力)とMP(精神力)をゴリゴリ削っていくんですよね。
もしせっかく素晴らしいケア、良い気づきができる仲間が、書類仕事や残業のせいで現場を去ってしまったら…悲劇でしかありませんよね。
3-2. 記録は未来のケアを支える「設計図」
日々の介護記録、「ただの面倒な作業」「早く終わらせたいルーティンワーク」
もしそう感じていたら、非常にもったいないかもしれません。
介護記録とは、より良いケアを提供するための「設計図」そのものなんです。
例えば、家を建てるとき、設計図がなければ柱の位置も壁の厚さも分かりませんよね。
それと同じで、日々の利用者さんの小さな変化、ふと漏らした一言、笑顔や不安な表情を記録した「設計図」がなければ、私たちは質の高いケアを組み立てることができません。
良い記録があれば、チーム全員が「この方には、こういう関わり方が合っている」「最近こういう変化があるから、医療と連携しよう」と、同じ方向を向いてケアを実践できます。
記録は、チームの力を最大限に引き出すための共通言語でもあるのです。
しかし、この重要な「設計図」作りが、ただの苦痛な作業になってしまったらどうでしょう?
それでは質の高いケアという家は建ちません。
AIは、この設計図作りに必要な「清書」や「整理」といった作業を、驚くほどの速さで代行してくれます。
私たちは日々の観察で得た情報(メモ)を渡すだけ。
あとはAIが、誰にでも分かりやすい設計図のたたき台を作ってくれるのです。
そうすれば、私たちはもっと「どんな家を建てようか?」という、ケアの最も創造的で大切な部分に時間と情熱を注げるようになります。
3-3. 国も後押しする時代の流れ:「介護DX」の波に乗ろう
「AIとかDXとか、ウチの施設には関係ないよ」なんて思う方もいるかもしれません。
でも、ちょっと待ってくださいね。
厚生労働省も今、「介護現場の生産性を上げよう!」と、ICTやAIの導入をすごく後押ししているんです。これはもう、国全体が「介護の仕事のやり方を変えていこうぜ!」と言っているのと同じなんですよね。
20年前、ほとんどの人がガラケーだったのが、今やスマホが当たり前になったように…
介護現場でICT機器やAIツールを使うのも、ごくごく当たり前の光景になる時代が、もうすぐそこまで来ています。
この大きな波に乗り遅れないことは、これからの介護士にとって、とても大切なスキルになるはずです。
私の失敗談①:記録に追われ、一番大切なことを見逃しかけた新人時代
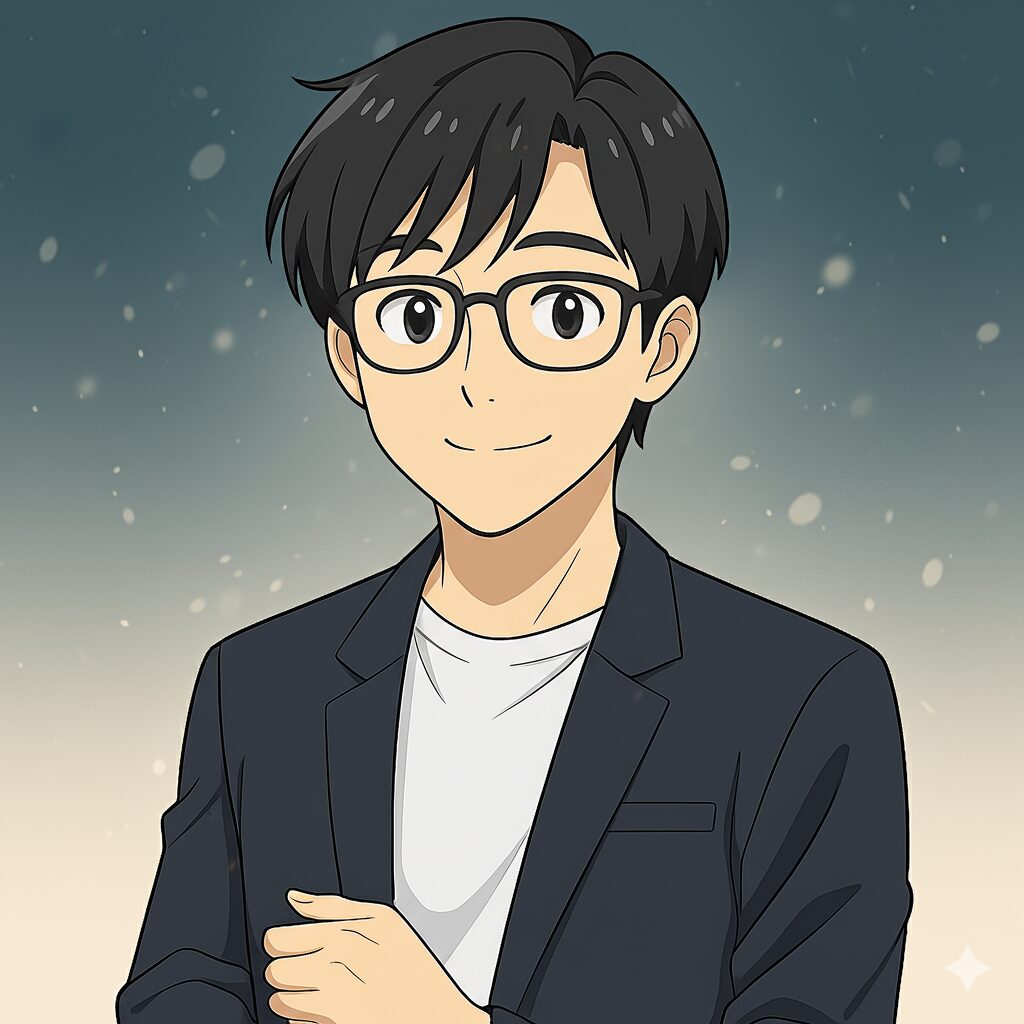
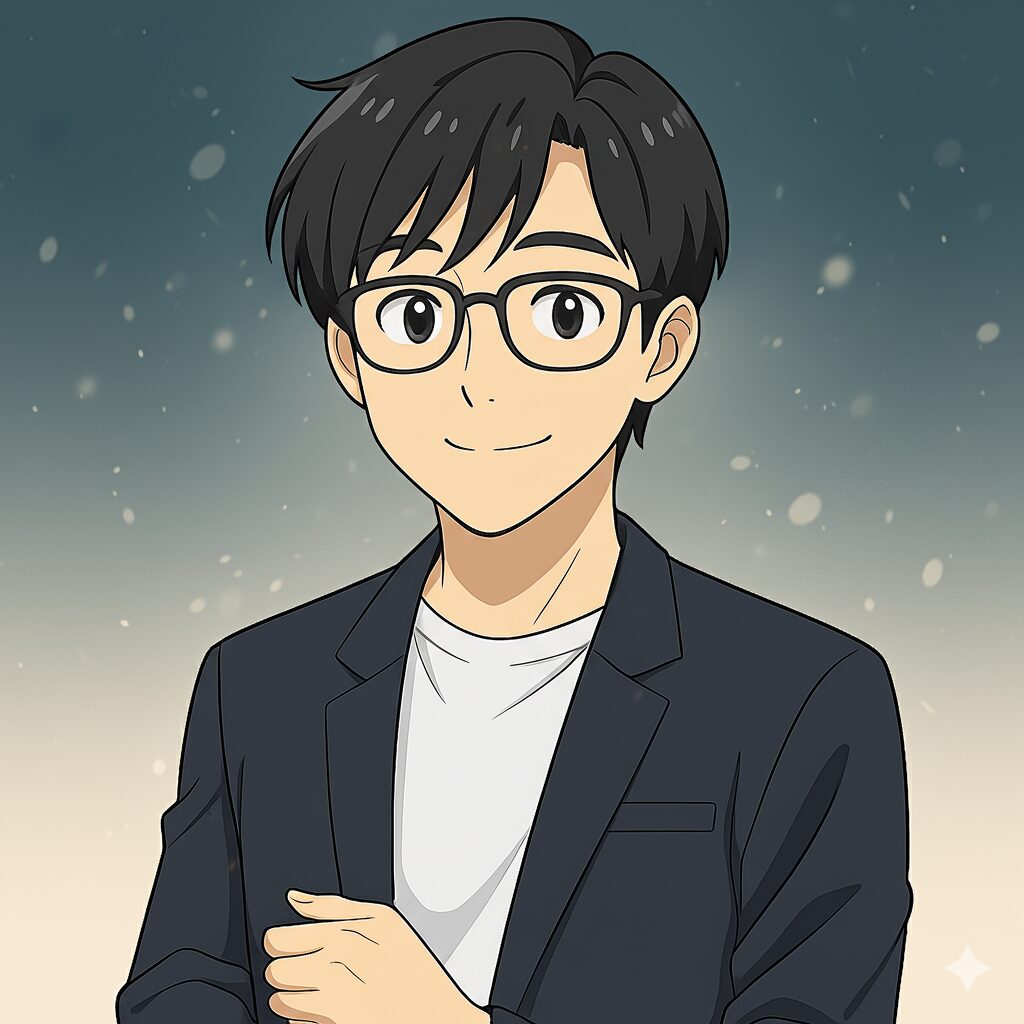
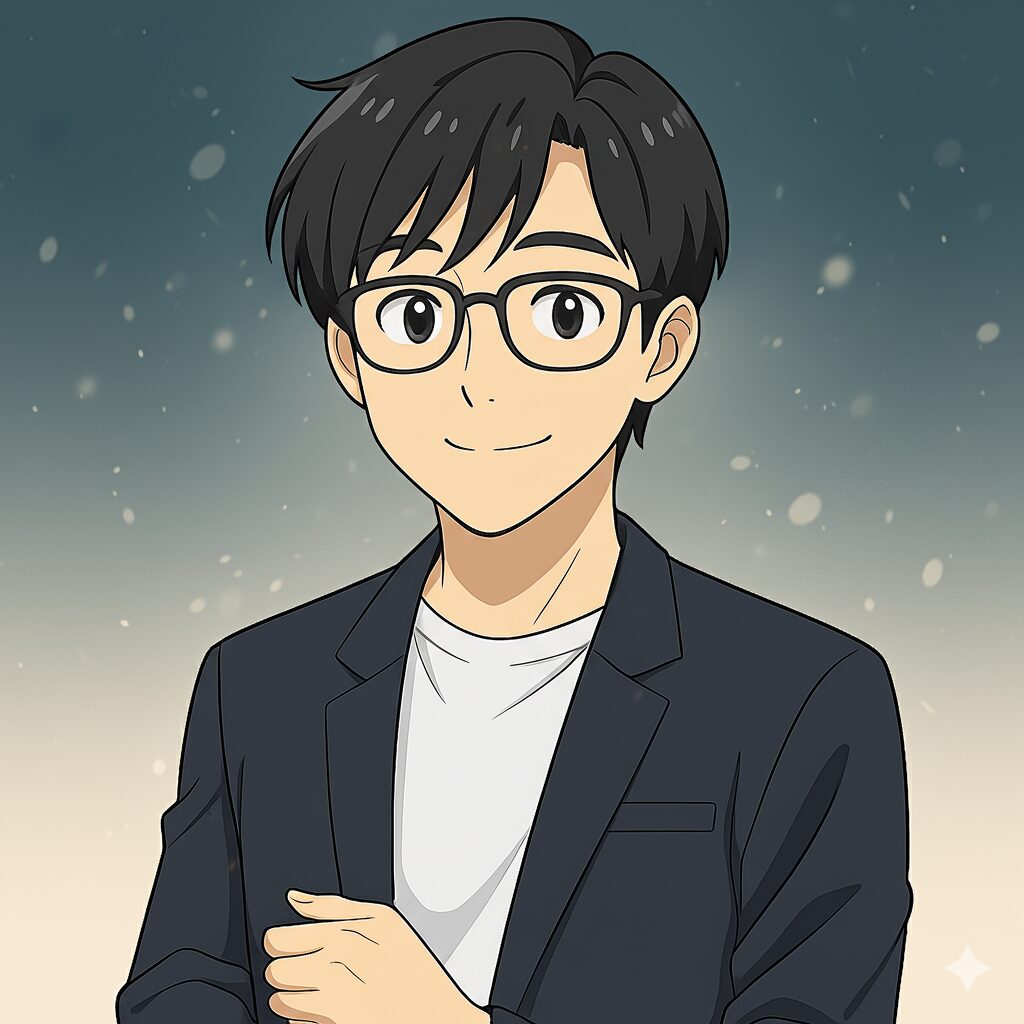
ここで少し、僕の恥ずかしい話をさせてください。
介護士になったばかりの頃、僕はとにかく日々の記録をこなすのに必死でした。
夕方になると、その日あったことを思い出しながら、必死に記録用紙を埋める毎日…
そんなある日、いつも穏やかなAさんが、食事を少し残されている日が続きました。
僕は「まぁ、そういう日もあるか」くらいにしか思わず、日々の記録には「食事摂取量8割」とだけ書いていました。しかし、ある日先輩から「やなぎくん、Aさんの記録、ずっと8割だけど、何か気づいたことない?」と声をかけられたんです。
ハッとしました。
僕は記録を「書く」ことに必死で、❝記録を「見る」、そして変化の連続性に「気づく」という視点❞が完全に欠けていたんです。幸い、すぐに多職種で情報共有し、Aさんの体調変化に早期に対応できましたが、一歩間違えば…と今でもヒヤリとします。
もしAIに日々の記録データを読み込ませて「Aさんの最近の傾向を教えて」と聞けていたら、「食事量が徐々に減少傾向にあります。口腔内の問題や体調不良の可能性があります」と、僕が見逃していたかもしれない視点を、AIが客観的に示してくれたかもしれない。
もちろん、最終的に気づき、行動するのは僕たち介護士であり、人間です。
でもAIは、その「気づき」のきっかけをくれる強力なサポーターになってくれるはずなのです。
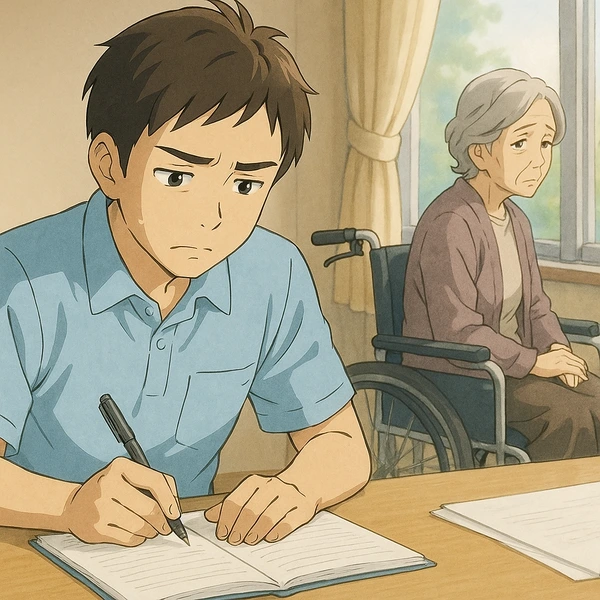
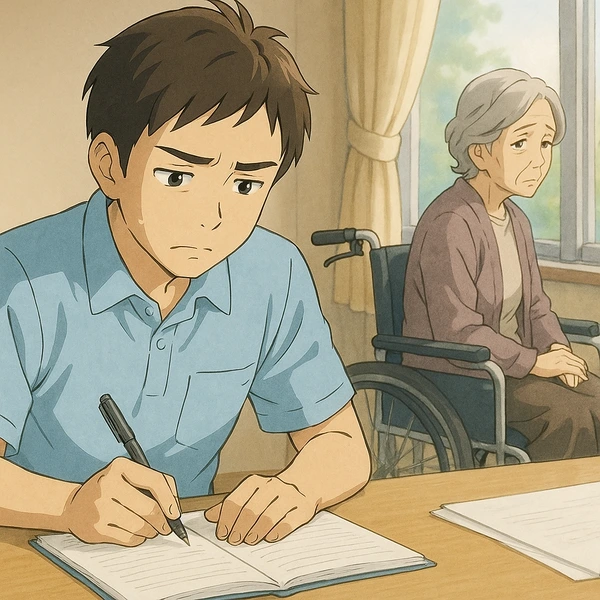
4. 【コピペOK】明日から使える!シーン別「プロンプト」集
お待たせいたしました!
ここからは、AIを「賢い部下」に育てるための具体的な指示の出し方、「プロンプト(AIへの指示文)」を伝授します。
コピペして、少し書き換えるだけで使えるように作ったので、ぜひ試してみてくださいね。
4-1. 冒険の準備:まずは無料のAIツールに登録しよう!
まずは武器を手に入れなければ冒険は始まりません。といっても、登録はとっても簡単。
以下のどちらかのサービスに登録すればOKです。どちらも無料で始められます。
- ChatGPT(チャットジーピーティー)
- Gemini(ジェミニ)
一番簡単なのは、Googleアカウントで登録する方法です。
登録方法は「ChatGPT 登録」などで検索すれば、分かりやすい解説サイトがすぐに見つかるので、ここでは割愛しますね。スマホのアプリもあるので、パソコンが苦手な方でも大丈夫ですよ。
4-2. AIを育てる3つの掟(最重要ポイント)
プロンプトを紹介する前に、AIと付き合う上で絶対に守ってほしい「3つの掟」をお伝えしておきますね。
これを守るだけで、AIの回答の質が劇的に変わります。
- 掟1:「あなたはプロのケアマネです」と役割を与えること
- AIに役割を与えることで、その道のプロとして回答してくれるようになります。
これは本当に効果絶大なので、必ずプロンプトの最初に書きましょう。
- AIに役割を与えることで、その道のプロとして回答してくれるようになります。
- 掟2:「箇条書きで」「表形式で」など出力形式を具体的に指示すること
- どういう形で答えてほしいかを明確に伝えることで、あなたが望む形の回答が得られやすくなります。「〇〇について教えて」よりも「〇〇について、メリットとデメリットを箇条書きで教えて」の方が、断然分かりやすいですよね。
- 掟3:【鉄則】個人名・施設名などの個人情報は絶対に入力しないこと
- これが一番大事です。AIに教えた情報は、AIの学習に使われてしまう可能性があります。
利用者さんや職員さんの名前、施設名、住所など、個人が特定できる情報は絶対に入力しないでください。「A様」「B施設」のように、必ず仮名や記号に置き換えて使いましょう。
- これが一番大事です。AIに教えた情報は、AIの学習に使われてしまう可能性があります。
4-3.【初級編】日々の介護記録・連絡帳を5分で仕上げるプロンプト術
まずは肩慣らし。日々の記録をサクッと作るプロンプトです。
▼プロンプト(コピーして使ってください)
あなたはプロの介護福祉士です。
以下の箇条書きの情報を基に、介護記録として自然で丁寧な文章を作成してください。
#対象者
A様(80代・女性・車椅子利用)
#本日の様子
・午前中、ホールで他の利用者と談笑。笑顔多く見られる。
・昼食は主食・副菜ともに全量摂取。
・午後レク(風船バレー)には意欲的に参加。若い頃バレー部だったと話す。
・夕方、少し疲れた表情で「今日は楽しかったけど、疲れたわ」との発言あり。
#出力形式
・ですます調で、客観的な事実とご本人の発言を分けて記述してください。
・文字数は200文字程度でお願いします。
▶︎AIの回答例
A様は本日、午前中はホールにて他の利用者様と談笑され、笑顔が多く見られました。昼食は全量摂取されています。午後のレクリエーション(風船バレー)には意欲的に参加され、「若い頃はバレー部だったのよ」と楽しそうに話されていました。夕方には「今日は楽しかったけど、疲れたわ」とのお話があり、やや疲れたご様子も見受けられました。
▼ポイント
このままでも十分ですが、ここにあなたしか知らない「観察」を加えると、さらに素晴らしい記録になります。「笑顔が多く見られ、特に〇〇さんとお話しされている時は声を出して笑っていました」のように、AIの骨子に肉付けしていくイメージです。
4-4.【中級編】ヒヤリハット・事故報告書を冷静に、構造的に書くプロンプト術
いざ書くとなると手が止まりがちなのが報告書ですよね。
AIに客観的な視点で整理してもらいましょう。
▼プロンプト(コピーして使ってください)
あなたはリスクマネジメントを専門とする介護コンサルタントです。
以下の情報を基に、ヒヤリハット報告書を作成してください。
#発生日時
本日14:30頃
#発生場所
居室から食堂へ向かう廊下
#当事者
B様(90代・男性・歩行器利用・軽度の認知症あり)
#状況
・食堂へ移動中、前方を歩いていた他の利用者に気を取られ、足元の段差に気づかず転倒しそうになった。
・近くにいた職員Cがすぐに気づき、体を支えたため転倒には至らなかった。怪我もなし。
#出力形式
以下の項目に沿って、構造的に記述してください。
1. 発生状況(5W1Hを明確に)
2. 発生の直接的な原因
3. 背景にある要因(環境要因・本人要因)
4. 再発防止策(具体的な対策を3つ提案)
▶︎AIの回答例
- 発生状況: 本日14:30頃、B様が居室から食堂へ向かう廊下を歩行器で移動中、前方の利用者に注意が向いたことで足元の段差に気づかず、バランスを崩し転倒しそうになった。職員Cが即座に体を支え、転倒・負傷はなかった。
- 直接的な原因: 前方への脇見による、足元への注意不足。
- 背景にある要因:
- (環境要因)廊下にわずかな段差があること。
- (本人要因)軽度の認知症による注意力の散漫。
- 再発防止策:
- 段差部分に注意喚起のテープを貼り、視覚的に分かりやすくする。
- 人通りの多い時間帯の移動は、職員が付き添う体制を検討する。
- B様の移動ルートについて、段差のないルートがないか再検討する。
▼ポイント
AIは原因分析や再発防止策の提案が非常に得意です。
自分一人では思いつかなかった視点を与えてくれることも多く、報告書の質を格段に上げてくれます。
4-5.【上級編】ケアプラン(第2表)の骨子をAIと一緒に作るプロンプト術
ケアプラン作成はケアマネの専門領域ですが、その「たたき台」をAIに作ってもらうことで、大幅な時間短縮が可能です。ここでは、立場別に2つのプロンプトをご紹介します。
4-5-1. 【地域ケアマネ編】在宅生活を支えるプロンプト術
在宅での生活を継続するための、多様な社会資源を活用したプランニングが求められます。
▼プロンプト(コピーして使ってください)
あなたは経験豊富な地域包括支援センターの主任ケアマネージャーです。
以下の利用者情報を基に、在宅生活を継続するためのケアプラン第2表の「長期目標」「短期目標」「サービス内容」の原案を作成してください。
#利用者情報
・C様(80代・男性・要介護3)
・妻と二人暮らし。日中はほとんどベッドで過ごしている。
・本人の希望:「天気がいい日は、昔よく行った近所の公園まで散歩したい」
・課題:下肢筋力の低下により、屋内での歩行も不安定。閉じこもりがちで他者との交流が減少し、介護する妻の負担も大きい。
#出力形式
・長期目標(期間:6ヶ月)を5つ提案してください。
・短期目標(期間:3ヶ月)を5つ提案してください。
・上記の目標の中から1つを選び、それを達成するための具体的なサービス内容(サービス種別、内容、頻度)を提案してください。
▶︎AIの回答例
【長期目標案(期間:6ヶ月)】
- 妻の介助または一人で、近所の公園(約150m)まで安全に散歩に行くことができる。
- 地域の老人会の定例会に月1回参加し、近隣住民との交流を楽しむ。
- 自宅の庭で、椅子に座ってできる範囲の園芸活動を週に1回行う。
- 日中の離床時間を4時間以上確保し、リビングで趣味の囲碁や読書をして過ごす。
- 妻の介護負担が軽減され、夫婦ともに心身のゆとりを持って在宅生活を継続できる。
【短期目標案(期間:3ヶ月)】
- 転倒の不安なく、手すりや歩行器を使って屋内を安定して10m歩行できるようになる。
- デイサービスの機能訓練に週2回参加し、下肢筋力の向上とバランス能力の改善を図る。
- 手すりを利用し、見守りのもとでトイレへの移乗が安定してできるようになる。
- 妻と一緒に、自宅前の道路を5分程度、安全に歩くことができる。
- 介護者である妻が、レスパイトケアとして週に半日、自分のための時間を持てる。
【短期目標1を達成するためのサービス内容案】
- サービス種別: 訪問リハビリテーション
- 内容: 理学療法士による下肢筋力強化訓練と、屋内での安全な歩行方法の指導。福祉用具(歩行器など)の適合状態の確認と調整。
- 頻度: 週2回
- サービス種別: 通所介護(デイサービス)
- 内容: 集団体操や個別機能訓練への参加を通じた身体機能の維持・向上。他者との交流機会の提供による社会的孤立感の軽減。
- 頻度: 週2回
- サービス種別: 福祉用具貸与
- 内容: 廊下やトイレ、玄関への手すりの設置。
- 頻度: 導入時
▼ポイント
在宅のケースでは、本人の身体機能だけでなく、家族の介護力や社会資源の活用など、多角的な視点が重要です。AIに複数の目標案を出させることで、本人・家族との面談時に、より具体的な選択肢を提示できます。
4-5-2. 【施設ケアマネ編】施設生活を豊かにするプロンプト術
施設という環境の中で、その人らしい生活をどう実現するか、集団生活と個別性の両立がポイントになります。
▼プロンプト(コピーして使ってください)
あなたは経験豊富な特別養護老人ホームの施設ケアマネージャーです。
以下の利用者情報を基に、施設での生活を豊かにするためのケアプラン第2表の「長期目標」「短期目標」「サービス内容」の原案を作成してください。
#利用者情報
・D様(80代・女性・要介護4)
・1ヶ月前に入所。新しい環境にまだ馴染めず、日中は自室で過ごすことが多い。
・本人の希望:「昔のように、編み物をまたやりたい。でも、目が悪くなって細かい作業は難しいかも…」
・課題:他者との交流を避ける傾向があり、日中の活動性が低下している。手指の巧緻性の低下。
#出力形式
・長期目標(期間:6ヶ月)を5つ提案してください。
・短期目標(期間:3ヶ月)を5つ提案してください。
・上記の目標の中から1つを選び、それを達成するための具体的なサービス内容(サービス種別、内容、頻度)を提案してください。
▶︎AIの回答例
【長期目標案(期間:6ヶ月)】
- 施設内の手芸クラブに参加し、自分の作品を完成させ、達成感を得る。
- ホールで過ごす時間が1日2時間以上になり、気の合う友人と談笑する場面が見られる。
- 家族が面会に来た際に、施設での楽しい出来事を自分から話すことができる。
- 自分の役割(洗濯物たたみ、配膳の手伝いなど)を持つことで、施設生活にやりがいを感じられる。
- 職員や他の利用者と安心して関わることができ、施設を「第二の我が家」と感じられる。
【短期目標案(期間:3ヶ月)】
- 週に1回、職員と一緒に、指先を使う簡単なレクリエーション(おはじき、お手玉など)に参加する。
- 視力が低下していても取り組みやすい、太い毛糸を使った「指編み」に挑戦する。
- 食事の際、同席者と一言二言、挨拶や会話を交わすことができる。
- 職員と一緒に、クラブ活動の様子を5分間見学する。
- 昔の編み物の作品を職員に見せながら、思い出を語る機会を持つ。
【短期目標2を達成するためのサービス内容案】
- サービス種別: 施設サービス(個別対応)
- 内容: 介護職員がマンツーマンで、D様のペースに合わせて指編みの方法を伝える。作業療法士と連携し、手指の巧緻性を維持・向上させるためのアドバイスをもらう。
- 頻度: 週2回(午後の個別活動時間)
- サービス種別: 施設サービス(環境整備)
- 内容: 作業に集中できるよう、手元が明るくなるデスクライトや、滑り止めのマットを準備する。
- 頻度: 随時
- サービス種別: 施設サービス(精神的ケア)
- 内容: 小さなことでも「すごいですね」「綺麗にできていますね」と具体的に褒め、意欲と自己肯定感を高める声かけを行う。
- 頻度: 毎日
▼ポイント
施設ケアプランでは、集団生活の中でのQOL(生活の質)向上が鍵です。
本人の「やりたい」という気持ちを起点に、多職種(介護、看護、リハビリ専門職など)とどう連携していくか、AIにアイデアを出してもらうと、プランに厚みが出ます。
私の成功談②:AIがくれた「50分」が、チームを変えた
最後に、僕がAIのおかげでできた成功談をお話させてください。
僕が主任をしていた時、毎週の職員会議の議事録作成が悩みの種でした。
会議で話しながらメモを取り、終わった後に1時間近くかけて清書する。この作業が、本当に負担だったんです。
ある日、ダメ元で会議のメモ(箇条書き)をAIに渡し、「このメモを基に、会議の議事録を作成して」とお願いしてみました。すると、どうでしょう。
わずか10分足らずで、要点がまとまった非常に分かりやすい議事録のドラフトが出来上がったんです。
ちょっと感動しちゃいました。
今まで1時間かかっていた作業が10分に。生まれた「50分」という時間。
その日、僕はその時間を使って、最近元気がないように見えた新人スタッフに「最近どう?」と声をかけ、じっくり話を聞くことができました。
すると彼女は、「実は、〇〇さんのケアで悩んでいて…」と、ずっと一人で抱えていた悩みを打ち明けてくれたんです。その場で一緒に解決策を考え、彼女の表情がパッと明るくなったのを見た時、僕は思いました。
AIがくれたのは、単なる業務効率化じゃない。職員と向き合い、チームの心を繋ぐための「時間」をくれたんだ、と。これこそ、僕がAI活用を皆さんに伝えたい、一番の理由です。
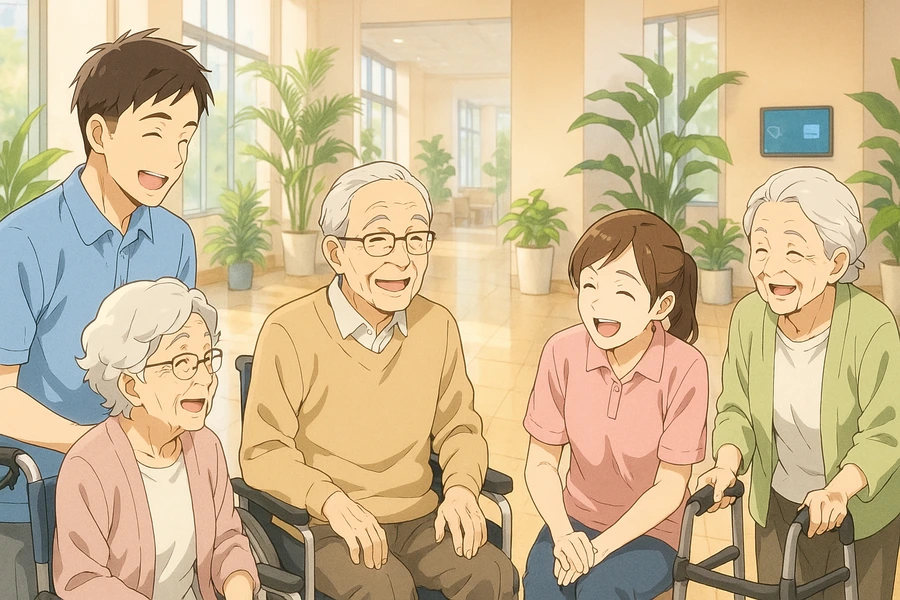
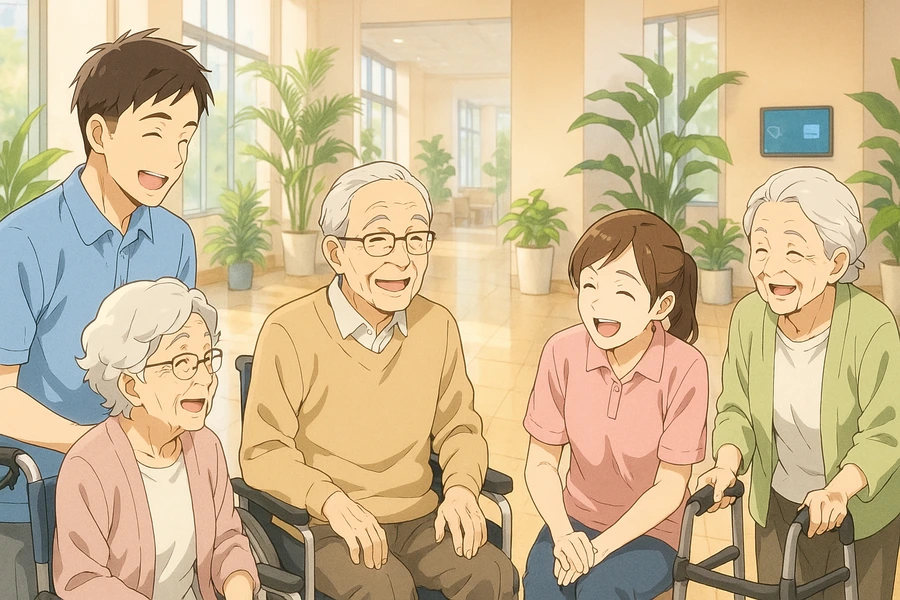
5. AIは優秀な部下。でも、指導者はあなたです。
ここまで、AIの具体的な使い方を見てきました。本当に便利ですよね。他にもイラストを描いたり動画を作ったり…
他の活用方法についてはまた機会があれば記事にしたいと思います。
でも、忘れてはいけないのは、AIはあくまで「思考を補助するツール」だということです。
僕はよく、AIを「万能包丁」に例えます。野菜も肉も魚も切れる、すごく便利な道具です。
でも、その包丁を使って、素材の味を最大限に引き出す繊細な飾り切りをしたり、食べる人の気持ちを考えて盛り付けを工夫したりするのは、料理人である人間にしかできません。
AIが提示する60点のたたき台。
それに、あなたの専門知識や経験、そして何より利用者さん一人ひとりへの温かい想いを込めて、100点のケアに仕上げていく。その最後のひと手間こそが、私たち介護のプロの真骨頂です。
▼AIに任せる仕事 vs 人間にしかできない仕事
| AIに任せるべき仕事 | 人間にしかできない仕事 |
|---|---|
| 定型的な書類作成 | その人の人生観や価値観を尊重する |
| 情報の整理・構造化 | 表情や声のトーンから気持ちを察する |
| 文章のドラフト作成 | 利用者の手を握り、温もりを伝える |
| データに基づく客観的な提案 | ユーモアを交えた会話で場を和ませる |
| アイデアの壁打ち相手 | 気持ちに寄り添い、静かに傾聴する |
AIを賢く使いこなして、私たち人間にしかできない、もっと温かいケアに時間を使いませんか?
【お悩み解決Q&A】AI活用「これってどうなの?」
- 個人情報を入れずに、どうやって個別性のある文章が作れるの?
-
確かにそこは気になるところですよね!
コツは、「個人を特定できない範囲で、情報を具体的にする」ことです。
例えば、「田中さん(85歳・特養に入居中)」と書くのはNGです。 代わりに、「80代・女性・施設入所中・車椅子を利用」のように、属性情報を組み合わせることで、AIはかなり具体的な状況をイメージしてくれます。「元教師でプライドが高い一面がある」といったパーソナルに関する情報を加えると、さらに個別性の高い回答が期待できますよ。 - AIが書いた文章って、他の人と被ったり、手抜きだと思われたりしない?
-
AIが作った文章をそのままコピペするだけでは、そう思われる可能性はあります。
大事なのは、先ほどもお伝えした通り「AIの回答はたたき台」と考えることです。
AIが作った骨子に、あなた自身の言葉や観察、感情を肉付けしていく。
「〇〇様が笑顔で話されていました」というAIの文章に、「その時の、本当に嬉しそうなシワの寄った笑顔が、私の心にも温かく残っています」と一言加えるだけで、それはもう世界に一つだけの、あなたの記録になります。 - パソコンが本当に苦手なんですが、それでも使えますか?
-
全く問題ありませんよ!
ChatGPTもGeminiも、スマートフォンのアプリがあります。
LINEで友達とメッセージをやり取りするような感覚で、AIに質問したり、お願いしたりすることができます。音声入力を使えば、キーボードを打つ必要すらありません。「今日の会議の要点をまとめて」とスマホに話しかけるだけで、議事録の原案が作れる。そんな時代なんです。ぜひ一度、アプリストアで検索してみてください。
6. まとめ:今日から始めるAI活用、最初の一歩
ここまで長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。
最後に、この記事でお伝えした大切なことを、もう一度振り返っておきましょう。
- 生成AIは、正しいプロンプト(指示)で使えば、介護の書類業務を劇的に効率化してくれる「賢い部下」になる。
- 付き合う上での絶対のルールは「個人情報を入力しない」こと。匿名化を徹底しよう。
- AIが出すのはあくまで「60点のたたき台」。専門職としての知識と経験、想いを加えて100点に仕上げるのは、あなた自身。
- AIで生まれた時間を使って、人間にしかできない温かいコミュニケーションや、質の高いケアを実践しよう。自分へのケアも忘れずに。
「よし、やってみよう!」と思ってくれたなら、まずは最初の一歩を踏み出してみませんか?
完璧を目指さなくて大丈夫です。
今日の夜勤の申し送り事項を、試しにAIに要約させてみる。
あるいは、「高齢者向けの簡単な体操のアイデアを5つ教えて」と話しかけてみる。
そんな小さな成功体験が、あなたとAIとの最高のパートナーシップの始まりになります。
▼こちらの記事もオススメです💡
介護記録の書き方についてや、サポートに役立つ「AI介護記録アシスタント」というツールが載っています!
誰でも簡単に使えるように作りましたので、ぜひ一度ご覧ください♪あわせて読みたい
7. おわりに:新しい時代の介護を、一緒に作っていきましょう
近年は特にテクノロジーは、すごいスピードで進化していきますよね。
10年後、介護現場は今とは全く違う景色になっているかもしれません。
でも、どれだけAIが進化して、便利なロボットが導入されても、変わらないものがあると僕は考えています。
それは、人の心を思う、人の心です。
利用者さんの不安な気持ちに寄り添い、その人の手をそっと握る温かさ。
目を見て、うんうんと深く頷きながら話を聴く優しさ。
こればかりは、どんなに高性能なAIにも真似することはできません。
テクノロジーは、私たちの仕事を奪うものではなく、私たちがもっと「人間らしい仕事」に集中できるように手助けしてくれる、最高の仲間です。
AIという新しい仲間と一緒に、もっと創造的で、もっと人間味あふれる温かい介護を。
この記事を読んでくれたあなたと一緒に作っていけたら、とっても嬉しいです。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。


追伸:もう少しだけ、お付き合いください
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!
この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。
▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。
▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。
もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!
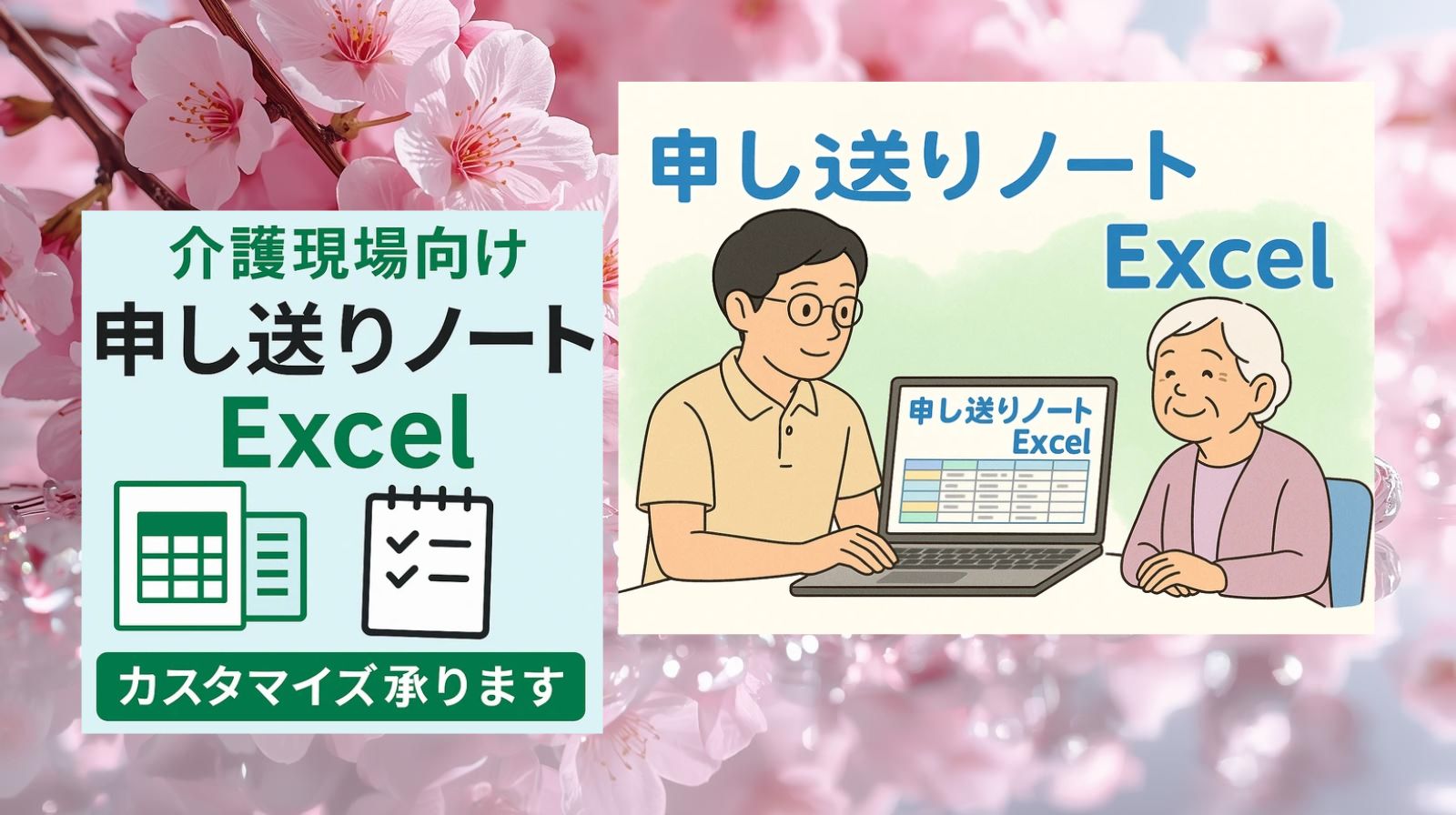

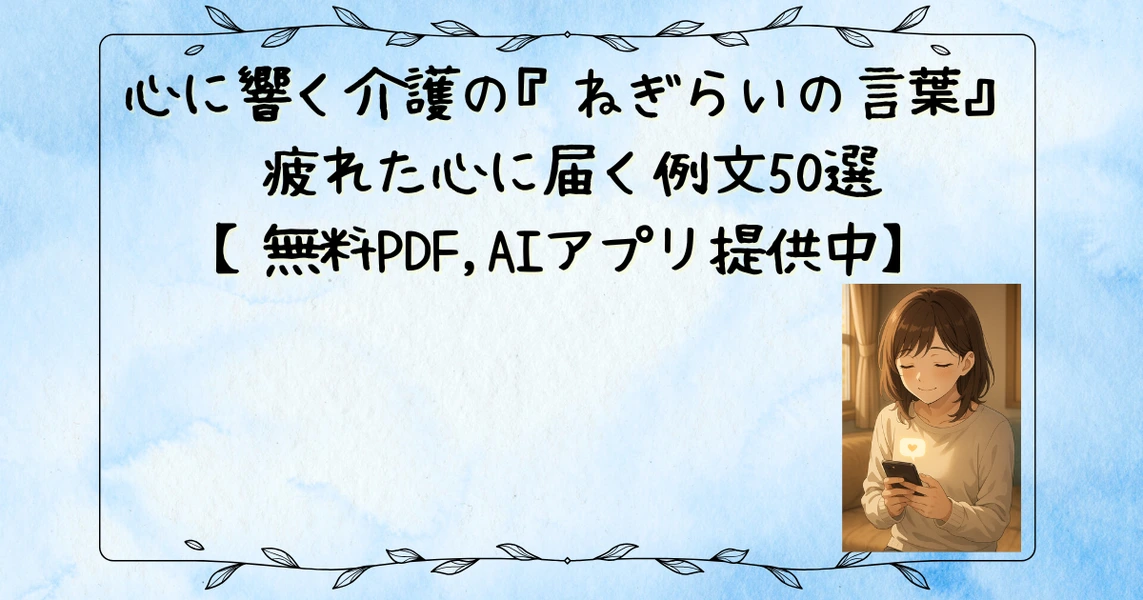


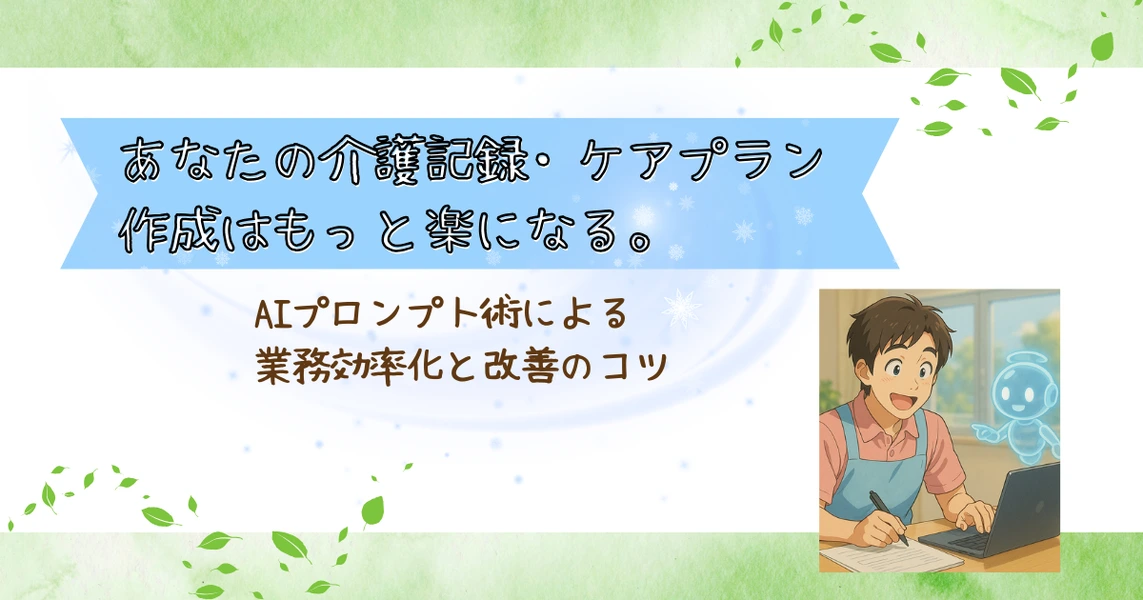

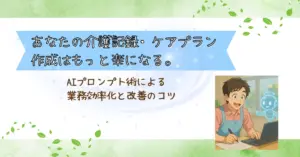
コメント