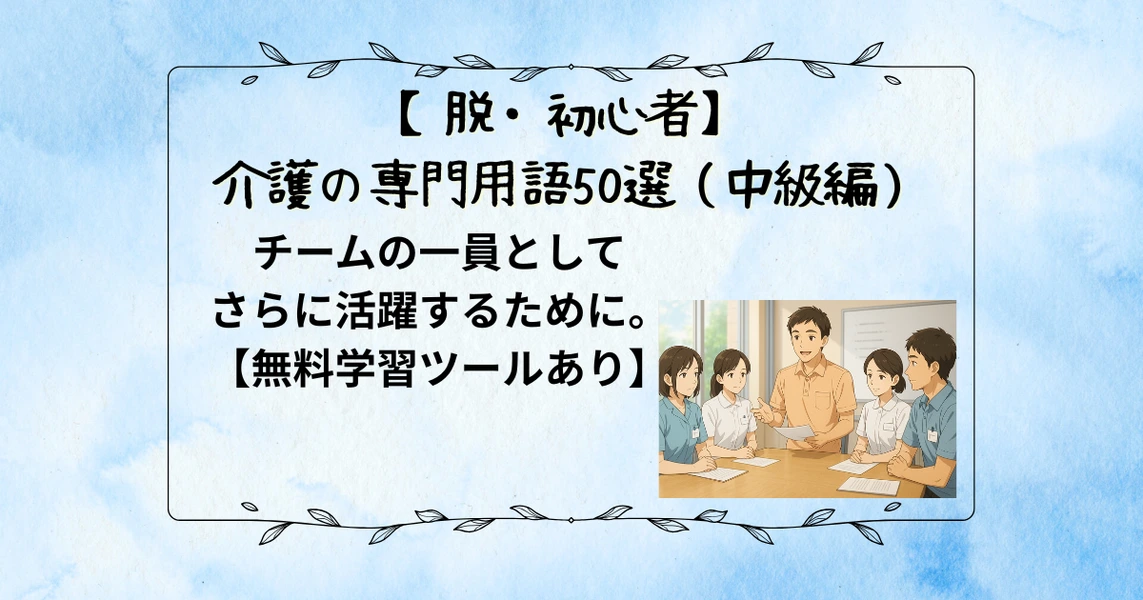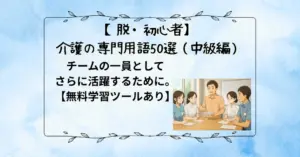1. はじめに:基本を覚えたあなたへ、次の一歩
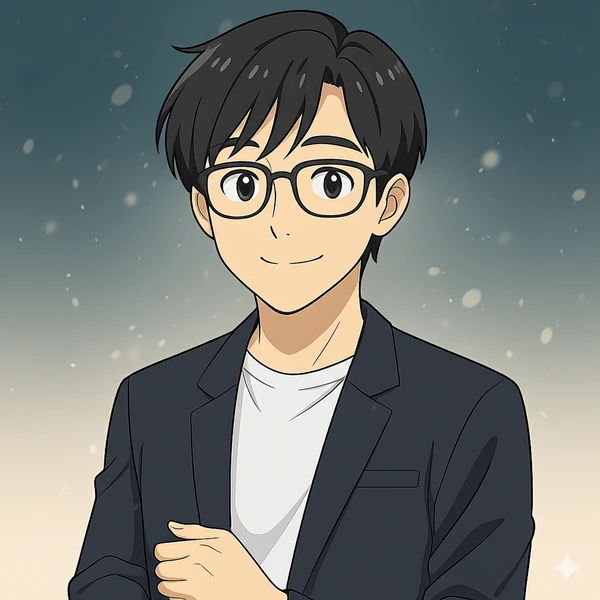
こんにちは!
元ITエンジニアで現役介護福祉士のやなぎです。
前回の「必須専門用語50選」は、お役立ていただけましたでしょうか?
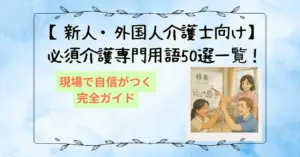
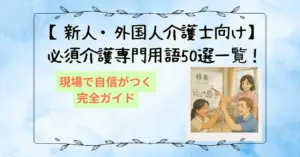
基本の言葉を覚え、日々のケアに少し自信がついてきた頃かもしれませんね。
※そして、今あなたは、こんな場面に遭遇していませんか?
「看護師さんやリハビリの先生の話が、まだ少し難しい…」
「サービス担当者会議で、知らない言葉が飛び交っている…」
「利用者さんの、より複雑な状態をどう表現すればいいんだろう?」
その気持ち、ステップアップしている証拠です!
基本をマスターした今だからこそ、次の中級レベルの言葉を学ぶことで、あなたの介護の質はもっともっと向上しますよ。
この記事では、あなたの「もっと知りたい!」という意欲に応えるために、以下の内容をまとめました。
- 医療・リハビリ・看取りなど、より専門的な場面で使う用語50選
- 言葉の背景にある制度や考え方の簡単な解説
- カンファレンスや記録ですぐに使える具体的な例文
この記事を読み終える頃には、多職種との連携がもっとスムーズになり、チームの一員として、より深くケアに関われるようになっているはずです。
一緒にレベルアップしていきましょう!
2. 結論:なぜ中級レベルの専門用語を知る必要があるのか
今回ご紹介する言葉は、基本的な身体介助の場面で毎日使うものではないかもしれません。
しかし、これらを知っているかどうかで、あなたの利用者さんへの理解度、そしてケアの専門性が大きく変わってきます。
例えば、利用者さんが「喀痰(かくたん)が多い」という情報を知っていれば、「ただの咳かな?」ではなく「窒息や誤嚥性肺炎のリスクがあるかもしれない」と考え、より注意深く観察し、必要であれば看護師に報告することができますよね。
また、サービス担当者会議で「IADL(手段的日常生活動作)の維持を目標に」という言葉が出たとき、その意味を理解していれば、「では、ご自身で買い物に行けるよう、歩行訓練を促そう」といった具体的なケアの提案に繋げることができます。
中級レベルの用語は、点(日々のケア)と点(専門的な情報)を結びつけ、利用者さんの生活全体を線で捉えるための知識です。これを学ぶことで、あなたは指示を待つだけでなく、自ら考え、提案できる専門職へと成長できるのです。
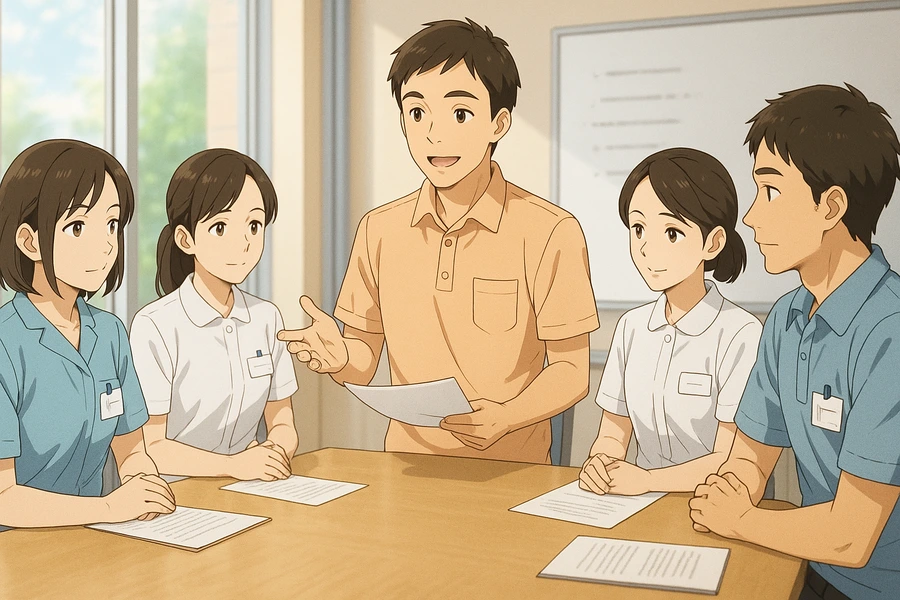
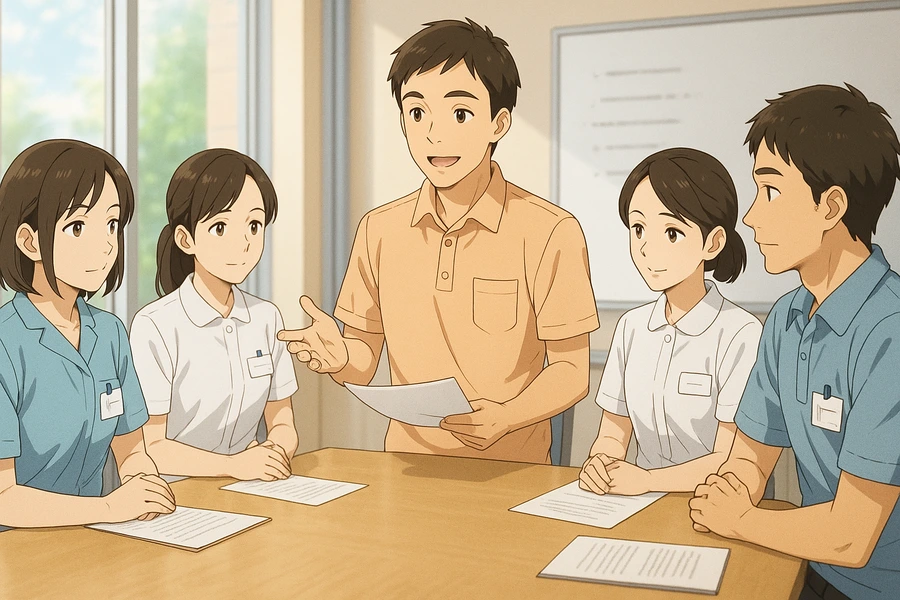
3. 【分野別】中級専門用語50選マスター講座
ここからは、より専門的な5つの分野に分けて、中級レベルの専門用語50選を例文付きでご紹介します。
まずは、あなたが一番興味のある分野からチェックしてみてくださいね。
3-1. 【医療・看護連携で使う言葉】(10選)
利用者さんの身体状態を、より医学的に理解するための言葉です。
| 用語(よみがな) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 喀痰(かくたん) | 気道から出る「たん」のこと。 | 「〇〇さん、喀痰が多くて少し苦しそうです」 |
| 経管栄養(けいかんえいよう) | 口から食事ができない場合に、鼻や胃に繋いだチューブで栄養を摂ること。 | 「佐藤さんは経管栄養なので、口腔ケアが特に重要です」 |
| 誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん) | 食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で炎症が起きること。 | 「発熱の原因は誤嚥性肺炎でした。嚥下状態に注意しましょう」 |
| 掻痒感(そうようかん) | 皮膚の「かゆみ」のこと。 | 「全身に掻痒感があるようで、頻繁に体を掻いています」 |
| 発赤(ほっせき) | 皮膚が赤くなること。褥瘡の初期症状など。 | 「仙骨部に3cm大の発赤が見られます。ナースに報告します」 |
| 血糖値(けっとうち) | 血液中のブドウ糖の濃度のこと。 | 「食前の血糖値測定とインスリン注射をお願いします」 |
| インスリン(いんすりん) | 血糖値を下げるホルモン。糖尿病の治療で注射薬として使う。 | 「高血糖のため、看護師がインスリンを注射しました」 |
| バルーンカテーテル(ばるーんかてーてる) | 尿道を通り膀胱に留置し、自動的に尿を排出させるための管。 | 「バルーンカテーテルが挿入されているので、感染症に注意が必要です」 |
| ストーマ (人工肛門)(すとーま) | 手術で腹部に造設された便の排泄口。 | 「ストーマのパウチ(袋)に便が溜まってきたので交換します」 |
| 頓服薬(とんぷくやく) | 症状がある時だけ、臨時で服用する薬(痛み止めなど)。 | 「膝の痛みの訴えがあったので、14時に頓服薬を服用されました」 |
3-2. 【リハビリ・機能訓練で使う言葉】(10選)
利用者さんの「できること」を維持・向上させるための言葉です。
| 用語(よみがな) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 廃用症候群(はいようしょうこうぐん) | 過度に安静にすることで、心身の機能が低下すること。 | 「長期臥床による廃用症候群を防ぐため、離床を促しましょう」 |
| ROM(あーるおーえむ) | Range of Motionの略。関節の動く範囲(関節可動域)。 | 「拘縮予防のため、PT(理学療法士)がROM訓練を行っています」 |
| IADL(あいえーでぃーえる) | 手段的日常生活動作。ADLより複雑な動作(買い物、電話、服薬管理など)。 | 「IADLの維持を目標に、ご自身での金銭管理を支援しています」 |
| PT/OT/ST(ぴーてぃー/おーてぃー/えすてぃー) | PT:理学療法士、OT:作業療法士、ST:言語聴覚士。リハビリの専門職。 | 「STによる嚥下訓練が、週に2回あります」 |
| 残存機能(ざんそんきのう) | 障がいが残っても、まだ保たれている心身の機能。 | 「残存機能を活かして、ご自身でできることを増やしていきましょう」 |
| 嚥下体操(えんげたいそう) | 飲み込む力を鍛えるための、口や舌の体操。 | 「食事の前に、誤嚥予防のために嚥下体操を行いましょう」 |
| 機能訓練(きのうくんれん) | 日常生活に必要な心身の機能を維持・回復させるための訓練。 | 「午後のレクリエーションは、機能訓練を兼ねた内容になっています」 |
| 歩行器(ほこうき) | 歩行を補助するための福祉用具。体を囲むタイプのもの。 | 「歩行器を使えば、ご自身の力で食堂まで移動できます」 |
| 自助具(じじょぐ) | 障がいがあっても自分で動作しやすくするための道具(柄の長いスプーン等)。 | 「自助具の活用で、ご自身で食事を完食できるようになりました」 |
| 片麻痺(かたまひ/へんまひ) | 体の左右どちらか半分に麻痺がある状態。 | 「右片麻痺の方の更衣介助では、脱健着患が原則です」 |
3-3. 【認知症ケアの応用で使う言葉】(10選)
認知症の方の心に、より深く寄り添うための言葉です。
| 用語(よみがな) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 中核症状(ちゅうかくしょうじょう) | 脳の細胞が壊れることで直接起こる症状(記憶障害、見当識障害など)。 | 「日付が分からなくなるのは、認知症の中核症状の一つです」 |
| 周辺症状(しゅうへんしょうじょう) | 中核症状に本人の性格や環境が影響して起こる症状。BPSDと同じ。 | 「環境の変化がストレスになり、周辺症状として暴力行為が現れた」 |
| ユマニチュード(ゆまにちゅーど) | 「見る・話す・触れる・立つ」を基本にしたフランス発祥のケア技法。 | 「ユマニチュードの考え方に基づき、ケアの際は必ず正面から目線を合わせる」 |
| バリデーション(ばりでーしょん) | 認知症の人の言動を、嘘や間違いと否定せず、感情に寄り添い受け入れる手法。 | 「『家に帰る』という訴えに対し、バリデーションで気持ちを受容する」 |
| 回想法(かいそうほう) | 昔の写真や音楽を使い、過去の楽しかった経験を語ってもらう心理療法。 | 「昔の歌謡曲をかけ、回想法を取り入れたレクリエーションを行う」 |
| 徘徊(はいかい) | 明確な目的がなく、歩き回ってしまうこと。 | 「徘徊ではなく、ご本人なりの目的があるのかもしれない、と考えてみよう」 |
| 弄便(ろうべん) | 便をいじってしまう行為。 | 「弄便の背景には、おむつの不快感があるのかもしれない」 |
| 帰宅願望(きたくがんぼう) | 施設などを「自分の家ではない」と感じ、「家に帰りたい」と訴えること。 | 「夕方になると、帰宅願望が強くなる方が多いです」 |
| せん妄(せんもう) | 急性の意識障害。幻覚を見たり、興奮したりする。体調不良時などに出やすい。 | 「高熱が原因で、夜間にせん妄の症状が見られました」 |
| 生活歴(せいかつれき) | その人が生まれてから現在まで、どのような人生を送ってきたかの歴史。 | 「その方の生活歴を知ることで、ケアのヒントが見つかります」 |
3-4. 【制度・書類で使う言葉】(10選)
介護保険やケアプランを理解するために不可欠な言葉です。
| 用語(よみがな) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 要介護認定(ようかいごにんてい) | 介護保険サービスを受けるために必要な、介護の必要度合いの認定。 | 「要介護認定の結果、要介護3から要介護2に変更になりました」 |
| ケアマネジャー(けあまねじゃー) | 介護の専門家。ケアプランの作成やサービスの調整を行う。介護支援専門員。 | 「来週、ケアマネジャーがモニタリングのために訪問します」 |
| サービス担当者会議(さーびすたんとうしゃかいぎ) | 利用者・家族と各担当者が集まり、ケアプランについて話し合う会議。 | 「明日の10時から、鈴木様のサービス担当者会議を行います」 |
| 身体拘束(しんたいこうそく) | 利用者本人の体を縛ったり、部屋に閉じ込めたりして行動を制限すること。原則禁止。 | 「身体拘束は、利用者さんの尊厳を著しく損なう行為です」 |
| 虐待防止(ぎゃくたいぼうし) | 高齢者への虐待を防ぐための取り組み。 | 「虐待防止委員会の研修が、来月開催されます」 |
| 個人情報保護(こじんじょうほうほご) | 利用者さんの氏名や病歴など、プライベートな情報を守ること。 | 「個人情報保護の観点から、利用者さんの話を外部でしないように」 |
| 主治医意見書(しゅじいいけんしょ) | 要介護認定の審査で使われる、主治医が書いた診断書。 | 「主治医意見書には、認知症についての記載があります」 |
| 短期目標/長期目標(たんきもくひょう/ちょうきもくひょう) | ケアプランに記載される、達成を目指すゴール。 | 「短期目標は『3ヶ月以内に、ポータブルトイレでの排泄が自立する』です」 |
| インフォームド・コンセント(いんふぉーむどこんせんと) | 十分な説明を受け、納得した上での同意。 | 「ご本人・ご家族へのインフォームド・コンセントが不可欠です」 |
| 守秘義務(しゅひぎむ) | 仕事で知り得た個人の情報を、外部に漏らしてはいけないという義務。 | 「私たち専門職には守秘義務があります」 |
3-5. 【看取り・ターミナルケアで使う言葉】(10選)
人生の最期に、穏やかに寄り添うための言葉です。
| 用語(よみがな) | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| 看取り(みとり) | 人生の最期を、自然な形で迎えられるように支援すること。 | 「当施設では、ご本人の希望に沿った看取り介護を行っています」 |
| ターミナルケア(たーみなるけあ) | 終末期医療・看護。延命目的ではなく、苦痛緩和などを中心に行うケア。 | 「医師の指示のもと、ターミナルケアに移行します」 |
| エンゼルケア(えんぜるけあ) | 亡くなられた後に行う、体の清拭や着替え、化粧などの死後処置。 | 「ご家族と一緒に、心を込めてエンゼルケアを行いました」 |
| 疼痛緩和(とうつうかんわ) | がんなどによる身体的な痛みを、医療用麻薬などを使って和らげること。 | 「疼痛緩和のため、定期的に痛み止めの薬を使います」 |
| グリーフケア(ぐりーふけあ) | 大切な人を亡くした家族など、遺族の悲しみに寄り添い支援すること。 | 「ご家族の気持ちに寄り添うグリーフケアも、私たちの仕事です」 |
| リビング・ウィル(りびんぐうぃる) | 生前の意思表示。人生の最期にどのような医療を受けたいか等を書面で示すこと。 | 「リビング・ウィルで、延命治療は望まないと表明されています」 |
| D.N.A.R(でぃーえぬえーあーる) | Do Not Attempt Resuscitationの略。心肺蘇生措置を行わないという意思表示。 | 「ご本人・ご家族の意思で、D.N.A.Rの方針となっています」 |
| 清拭(せいしき) | 入浴ができない場合に、蒸しタオルなどで体を拭いて清潔を保つこと。 | 「最期まで心地よく過ごせるよう、丁寧な清拭を心がけましょう」 |
| 臨終(りんじゅう) | 死に際、亡くなる間際のこと。 | 「昨夜、ご家族に見守られながら、穏やかに臨終を迎えられました」 |
| デスカンファレンス(ですかんふぁれんす) | 亡くなられた利用者さんのケアを、スタッフで振り返る話し合い。 | 「次回のデスカンファレンスで、佐藤様のケアについて振り返ります」 |
4. 言葉は、より深いケアへの扉を開く「鍵」
ここまで、中級レベルの専門用語50選を見てきました。
いかがでしたか?
難しいと感じる言葉も多かったかもしれませんね。
しかし、これらの言葉は、あなたを次のステージへ導いてくれる大切な「鍵」です。
- 「医療・看護」という扉を開けば、利用者さんの身体状態をより深く理解できます。
- 「リハビリ」という扉を開けば、利用者さんの可能性を最大限に引き出す支援ができます。
- 「看取り」という扉を開けば、人の人生の最期に尊厳を持って寄り添うことができます。
一つ一つの言葉を学ぶことは、これらの大切な扉を開けるための鍵を手に入れることと同じです。
焦る必要はありません。日々の業務の中で、一つでも多くの鍵を見つけ、使いこなせるようになっていきましょうね。


5. まとめ:明日からできる!中級用語マスターへの3ステップ
「覚えることが多すぎる!」と圧倒されないために、明日からできる具体的な学習ステップを3つご紹介します。
- ステップ1:まずは「自分の施設の利用者さん」に関係する言葉から覚える
あなたの周りに、経管栄養の方や、リハビリを頑張っている方はいませんか?
まずは、その方のケアに直接関係する言葉から調べてみましょう。
自分事として捉えることで、記憶に定着しやすくなります。 - ステップ2:カンファレンスや会議の「予習・復習」をしてみる
サービス担当者会議などの予定が分かったら、その利用者さんのケアプランを読み返し、わからない言葉を事前に調べてみましょう。
会議の後には、「今日のあの言葉は、こういう意味だったのか」と答え合わせができます。 - ステップ3:看護師やケアマネジャーに、勇気を出して質問してみる
専門分野の言葉は、その道のプロに聞くのが一番の近道です。
「お時間のある時に教えてください」と一声かければ、きっと誰もが喜んで教えてくれます。
あなたのその積極的な姿勢は、必ず評価されますよ。
【無料学習ツール】中級編もゲームで挑戦!「介護専門用語マスター道場」
この記事で学んだ中級レベルの専門用語50選を、もっと効率的に、もっと楽しく復習するための学習ツール「介護専門用語マスター道場(中級編)」もご用意しました!
カンファレンスの内容を深く理解したり、多職種との連携をスムーズにしたりするためには、言葉を「知っている」だけでなく「使える」レベルまで定着させることが大切です。
【このツールの3つの特徴】
- ① 2つのモードで専門知識を定着!
- じっくり自分のペースで復習できる「単語カードモード」
- ゲーム感覚で知識を確認できる「四択クイズモード」
- ② 苦手な専門分野を集中特訓!
- 「医療・看護連携」や「リハビリ」など、あなたが強化したい分野を絞って学習できます。
- ③ もちろん登録不要&完全無料!
- インストールや会員登録は一切不要。このページですぐに学習を始められます。
インプットとアウトプットを繰り返すことが、記憶を定着させる一番の近道です。 ぜひこのツールを繰り返し使って、確かな知識を身につけてくださいね!
⇩【無料学習ツール】はこちら⇩
介護専門用語マスター道場
【中級編】
用語
クリックして意味を見る
意味
例文
問題
スコア: 0
結果発表!
0 / 0
⇩介護専門用語中級編50個のPDFも配布しちゃいます!⇩
より専門的な5つの分野に分けて、中級レベルの専門用語50個をまとめたものです。
印刷してポケットに入れたり、デスクの前に貼ったりして、日々の学習にお役立てください。
6. おわりに:学び続けるあなたが、介護の未来を創る
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
基本をマスターし、さらに知識を深めようと学び続けるあなたの存在は、介護の現場にとって、そして利用者さんにとって、かけがえのない宝物になりますよ。
新しい言葉を学ぶことは、大変かもしれません。
でも、その学びの一つ一つが、あなたのケアを豊かにし、あなたをプロフェッショナルとして成長させてくれます。
この記事が、あなたの次の一歩を後押しする、心強い味方になれたなら、とても嬉しいです。
あなたの挑戦を、心から応援していますね!
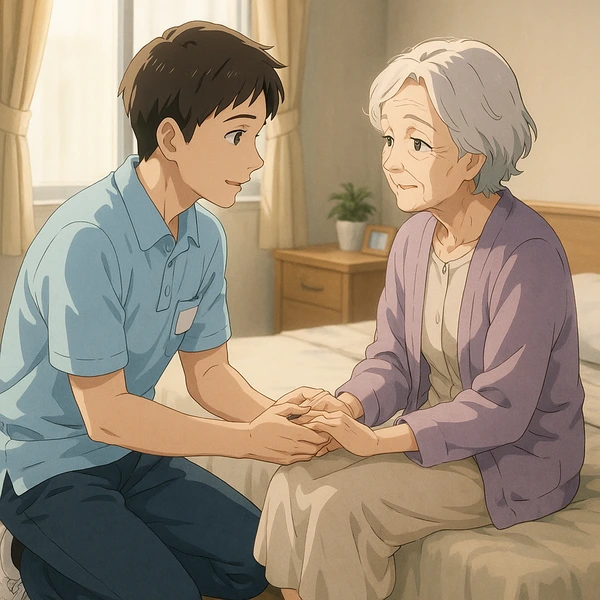
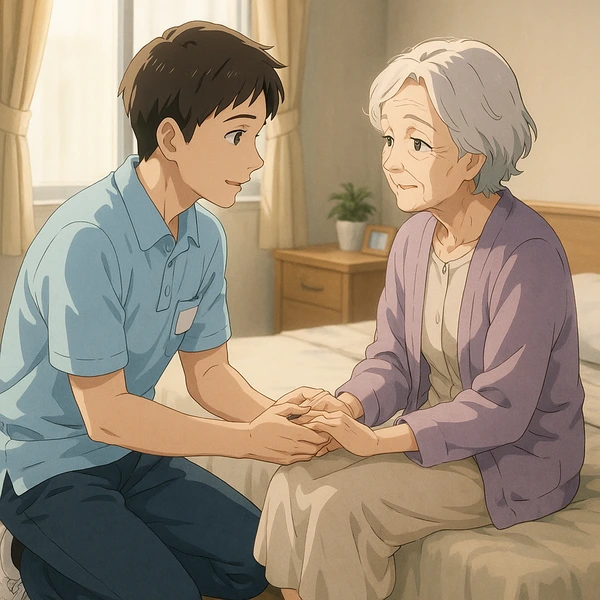
追伸:もう少しだけ、お付き合いください
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!
この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。
▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。
▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。
もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!