はじめに:なぜ専門用語があなたの介護を強くするのか?

こんにちは!
元ITエンジニアで、現役介護福祉士の「やなぎ」です。
特別養護老人ホームで主任をしながら、介護現場の負担をITで改善する活動をしています。
介護の現場に立つあなたは、今こんな風に感じていませんか?
「申し送りの内容が、まるで暗号みたい…」
「看護師さんやリハビリの先生の話が難しい…」
「カンファレンスで、知らない言葉が飛び交っている…」
その感覚、すごくよく分かります。
僕も新人時代は、毎日が初めて聞く言葉との戦いでした。
メモ帳はあっという間に真っ黒になり、外国人スタッフが言葉のニュアンスに戸惑う姿もたくさん見てきました。
でも、安心してください。
専門用語は、コツさえ掴めば必ず覚えられます。
そして、それを学ぶことは、あなたの介護士としてのキャリアを支える、最も重要で最も確実な土台作りなんです。
なぜ専門用語を学ぶ必要があるのか?
それは、専門用語が「チーム全員で、利用者さんの命と生活を守るための共通言語」だからです。
介護の現場は、あなた一人だけではありません。
日勤、夜勤のスタッフ、看護師、相談員、そして時には医師とも連携するまさにチームプレーの世界です。
もし、チームの中で一人ひとり使う言葉の意味が違っていたら、大切な情報がうまく伝わらず、大きな事故につながってしまうかもしれません。
例えば、食事の報告で「〇〇さん、お昼ご飯を全部食べました」と伝えるのと、「〇〇さん、昼食は完食でしたが、時々むせ込みが見られ、いつもより時間がかかっていました」と伝えるのでは、全く意味が違ってきますよね。
この小さな言葉の違いが、利用者さんの命を守ることに直結します。
そして、あなたが正確な言葉で報告・連絡・相談できることは、「この人はプロとして信頼できる」というチームからの評価に繋がるのです。
この記事で学べること
この記事では、新人からリーダー・管理者まで、すべての介護職が知っておくべき専門用語150選を、レベル別・場面別に整理してご紹介します。
- 第1章:新人・外国人向け|まずは覚えるべき必須50語
- 第2章:中級者向け|チームで活躍するための応用50語
- 第3章:リーダー向け|管理者・指導者のための専門50語
- 第4章:場面別|逆引き介護用語辞典
- 第5章:無料ツール|AIでいつでもどこでも専門用語を学習
全部一気に覚えようとせず、「あ、これは毎日聞く言葉だな」というものから、自分のペースでチェックしてみてくださいね。
この記事を読み終える頃には、言葉への不安が消えて、もっとケアそのものに集中できるプロとしての一歩を踏み出せるはずです。一緒に頑張っていきましょう!
第1章:【新人・外国人向け】まずは覚えるべき必須50語
まずは、介護の仕事を始めたばかりの方が、毎日のケアで必ず使う基本の言葉50選をご紹介します。
1-1. 【超基本】身体介助の言葉(15選)
毎日のケアで必ず登場する基本の言葉たちです。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 移乗 | いじょう | ベッドから車椅子などへ乗り移ること。 | 「〇〇さん、ベッドから車椅子に移乗しましょうか」 |
| 更衣 | こうい | 衣服を着替えること。 | 「朝の更衣を手伝いますね」 |
| 口腔ケア | こうくうけあ | 歯磨きやうがいなどで口の中を清潔にすること。 | 「食事が終わったので、口腔ケアをします」 |
| 整容 | せいよう | 身だしなみを整えること(洗顔、髪をとかす等)。 | 「朝食の前に、整容を済ませましょう」 |
| 排泄 | はいせつ | 尿や便を体外に出すこと。 | 「排泄の介助が必要な方を優先しましょう」 |
| 入浴 | にゅうよく | お風呂に入ること。 | 「本日の入浴担当は、田中さんと私です」 |
| 体位交換 | たいいこうかん | 寝ている人の体の向きを変えること。褥瘡予防が目的。 | 「2時間おきに体位交換をお願いします」 |
| 離床 | りしょう | ベッドから起き上がって離れること。 | 「日中はできるだけ離床して、活動量を増やしましょう」 |
| 臥床 | がしょう | ベッドに横になること。 | 「少し疲れたようなので、臥床を促しました」 |
| 食事介助 | しょくじかいじょ | 食事を摂るのを手伝うこと。 | 「山田さんは、食事介助が必要です」 |
| 水分補給 | すいぶんほきゅう | 水やお茶などを飲んでもらうこと。脱水予防。 | 「こまめに水分補給を促してください」 |
| 自立 | じりつ | 介助なしで、ご自身の力でできること。 | 「トイレまでは自立して歩行されています」 |
| 見守り | みまもり | 危険がないかそばで静かに見ていること。 | 「歩行が少し不安定なので、見守りをお願いします」 |
| 一部介助 | いちぶかいじょ | 部分的に手伝いが必要な状態。 | 「ズボンを上げるのに一部介助が必要です」 |
| 全介助 | ぜんかいじょ | すべての動作に手伝いが必要な状態。 | 「更衣は全介助となります」 |
1-2. 【観察のキホン】利用者の状態を表す言葉(15選)
利用者さんの変化に気づき、チームに正確に伝えるための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 患側 | かんそく | 病気や麻痺がある側。 | 「患側の腕が動かしにくいようです」 |
| 健側 | けんそく | 健康な、麻痺がない側。 | 「立ち上がる時は、健側の足に力を入れてもらいましょう」 |
| 麻痺 | まひ | 体の一部が動かなくなること。 | 「右半身に麻痺があります」 |
| 拘縮 | こうしゅく | 関節が固まって動きにくくなること。 | 「肘に拘縮があるので、無理に伸ばさないでください」 |
| 嚥下 | えんげ | 食べ物や飲み物を飲み込むこと。 | 「嚥下の状態を確認しながら、介助してください」 |
| 誤嚥 | ごえん | 食べ物などが誤って気管に入ること。 | 「むせ込みがあったので、誤嚥の可能性があります」 |
| BPSD | びーぴーえすでぃー | 認知症の行動・心理症状(徘徊、暴力、不安など)。 | 「夕方になると、BPSDで不穏になる傾向があります」 |
| 見当識障害 | けんとうしきしょうがい | 時間、場所、人がわからなくなること。 | 「見当識障害があり、ここがどこか混乱されています」 |
| バイタルサイン | ばいたるさいん | 生命兆候(体温、脈拍、血圧、呼吸)。 | 「起床時に、全員のバイタルサインを測定します」 |
| 傾眠 | けいみん | 声をかけると起きるが、放っておくと眠ってしまう状態。 | 「日中、傾眠されている時間が長いです」 |
| 不穏 | ふおん | 落ち着きがなく、興奮している状態。 | 「何か理由があるのか、少し不穏なご様子です」 |
| 褥瘡 | じょくそう | 床ずれのこと。 | 「仙骨部に褥瘡ができないよう、除圧が必要です」 |
| 浮腫 | ふしゅ | むくみのこと。 | 「足の浮腫が昨日より強くなっています」 |
| 便秘 | べんぴ | 便が数日間出ない状態。 | 「3日間排便がないので、便秘の可能性があります」 |
| 脱水 | だっすい | 体内の水分が不足している状態。 | 「唇が乾燥しているので、脱水を疑いましょう」 |
1-3. 【連携のキホン】記録・申し送りで使う言葉(10選)
チームで情報を共有し、一貫したケアを行うための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 申し送り | もうしおくり | 勤務交代時に、情報を引き継ぐこと。 | 「夜勤からの申し送りを始めます」 |
| ケアプラン | けあぷらん | 介護の計画書。 | 「ケアプランに沿って、自立支援を行います」 |
| アセスメント | あせすめんと | 利用者の情報を収集し、課題を分析すること。 | 「アセスメントをもとに、ケアプランを見直します」 |
| モニタリング | もにたりんぐ | ケアプランの効果や変化を観察・記録すること。 | 「排泄状況のモニタリング期間です」 |
| インシデント | いんしでんと | 事故につながりかねない、好ましくない出来事。 | 「薬の渡し忘れがあったため、インシデント報告書を作成します」 |
| ヒヤリハット | ひやりはっと | 事故にはならなかったが、ヒヤリとした、ハッとした出来事。 | 「廊下で転びそうになっていた。ヒヤリハットとして報告します」 |
| カンファレンス | かんふぁれんす | ケアについて話し合う会議。 | 「来週、ご家族を交えてカンファレンスを開きます」 |
| 多職種連携 | たしょくしゅれんけい | 医師、看護師、リハビリ職など、様々な専門職が協力すること。 | 「多職種連携で、在宅復帰を支援します」 |
| ADL | えーでぃーえる | 日常生活動作(食事、入浴、更衣など)。 | 「ADLは、ほぼ自立されています」 |
| QOL | きゅーおーえる | 生活の質、人生の質。 | 「QOLの向上を目指したケアを考えましょう」 |
1-4. 【重要原則】日本の介護の考え方を表す言葉(5選)
これは、利用者さんと私たち介護士自身を守るための、大切な「考え方」です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ボディメカニクス | ぼでぃめかにくす | 身体の動きの仕組み。最小限の力で介助する技術。 | 「腰を痛めないよう、ボディメカニクスを意識して」 |
| 脱健着患 | だっけんちゃっかん | 脱ぐときは健側から、着るときは患側から。麻痺がある方の更衣の原則。 | 「更衣の基本、脱健着患を忘れないでください」 |
| 自立支援 | じりつしえん | 利用者ができることは自身で行えるよう支援すること。 | 「何でもやってあげるのではなく、自立支援の視点が大切です」 |
| 尊厳の保持 | そんげんのほじ | 一人の人間として、その人らしさを尊重すること。 | 「認知症があっても、その方の尊厳の保持を第一に考えます」 |
| ノーマライゼーション | のーまらいぜーしょん | 障がいがあっても、誰もが当たり前に暮らせる社会を目指す理念。 | 「ノーマライゼーションの理念に基づき、地域交流を企画します」 |
1-5. 【応用編】現場特有の表現のニュアンスを知ろう(5選)
少し曖昧に聞こえますが、現場でよく使われる便利な言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 適宜 | てきぎ | その場の状況に合わせて、適切に行うこと。 | 「適宜、水分補給を促してください」 |
| 様子見 | ようすみ | すぐに判断せず、しばらく状態の変化を見ること。 | 「今は眠れているので、少し様子見にしましょう」 |
| 傾聴 | けいちょう | 相手の話に深く耳を傾け、理解しようと努めること。 | 「まずは利用者さんの訴えを傾聴することが大切です」 |
| 受容 | じゅよう | 相手の言動や感情を、否定せずありのまま受け止めること。 | 「興奮されている気持ちを、まずは受容しましょう」 |
| 共感 | きょうかん | 相手の気持ちに寄り添い、同じように感じようとすること。 | 「『寂しいんですね』と共感の言葉をかける」 |
第2章:【中級者向け】チームで活躍するための応用50語
基本の言葉を覚え、日々のケアに少し自信がついてきた頃かもしれませんね。
ここからは、より専門的な場面で使う中級レベルの用語50選をご紹介します。
2-1. 【医療・看護連携で使う言葉】(10選)
利用者さんの身体状態を、より医学的に理解するための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 喀痰 | かくたん | 気道から出る「たん」のこと。 | 「〇〇さん、喀痰が多くて少し苦しそうです」 |
| 経管栄養 | けいかんえいよう | 口から食事ができない場合に、鼻や胃に繋いだチューブで栄養を摂ること。 | 「佐藤さんは経管栄養なので、口腔ケアが特に重要です」 |
| 誤嚥性肺炎 | ごえんせいはいえん | 食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で炎症が起きること。 | 「発熱の原因は誤嚥性肺炎でした。嚥下状態に注意しましょう」 |
| 掻痒感 | そうようかん | 皮膚の「かゆみ」のこと。 | 「全身に掻痒感があるようで、頻繁に体を掻いています」 |
| 発赤 | ほっせき | 皮膚が赤くなること。褥瘡の初期症状など。 | 「仙骨部に3cm大の発赤が見られます。ナースに報告します」 |
| 血糖値 | けっとうち | 血液中のブドウ糖の濃度のこと。 | 「食前の血糖値測定とインスリン注射をお願いします」 |
| インスリン | いんすりん | 血糖値を下げるホルモン。糖尿病の治療で注射薬として使う。 | 「高血糖のため、看護師がインスリンを注射しました」 |
| バルーンカテーテル | ばるーんかてーてる | 尿道を通り膀胱に留置し、自動的に尿を排出させるための管。 | 「バルーンカテーテルが挿入されているので、感染症に注意が必要です」 |
| ストーマ(人工肛門) | すとーま | 手術で腹部に造設された便の排泄口。 | 「ストーマのパウチ(袋)に便が溜まってきたので交換します」 |
| 頓服薬 | とんぷくやく | 症状がある時だけ、臨時で服用する薬(痛み止めなど)。 | 「膝の痛みの訴えがあったので、14時に頓服薬を服用されました」 |
2-2. 【リハビリ・機能訓練で使う言葉】(10選)
利用者さんの「できること」を維持・向上させるための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 廃用症候群 | はいようしょうこうぐん | 過度に安静にすることで、心身の機能が低下すること。 | 「長期臥床による廃用症候群を防ぐため、離床を促しましょう」 |
| ROM | あーるおーえむ | Range of Motionの略。関節の動く範囲(関節可動域)。 | 「拘縮予防のため、PT(理学療法士)がROM訓練を行っています」 |
| IADL | あいえーでぃーえる | 手段的日常生活動作。ADLより複雑な動作(買い物、電話、服薬管理など)。 | 「IADLの維持を目標に、ご自身での金銭管理を支援しています」 |
| PT/OT/ST | ぴーてぃー/おーてぃー/えすてぃー | PT:理学療法士、OT:作業療法士、ST:言語聴覚士。リハビリの専門職。 | 「STによる嚥下訓練が、週に2回あります」 |
| 残存機能 | ざんそんきのう | 障がいが残っても、まだ保たれている心身の機能。 | 「残存機能を活かして、ご自身でできることを増やしていきましょう」 |
| 嚥下体操 | えんげたいそう | 飲み込む力を鍛えるための、口や舌の体操。 | 「食事の前に、誤嚥予防のために嚥下体操を行いましょう」 |
| 機能訓練 | きのうくんれん | 日常生活に必要な心身の機能を維持・回復させるための訓練。 | 「午後のレクリエーションは、機能訓練を兼ねた内容にしています」 |
| 歩行器 | ほこうき | 歩行を補助する道具。 | 「歩行器を使えば、ご自身でトイレまで行けます」 |
| 杖 | つえ | 歩行を支える道具。T字杖、四点杖など種類がある。 | 「T字杖を使って、見守りのもと歩行されています」 |
| 移動補助具 | いどうほじょぐ | 歩行器、杖、車椅子など、移動を助ける道具の総称。 | 「適切な移動補助具を選ぶことで、自立度が向上します」 |
2-3. 【認知症ケアで使う言葉】(10選)
認知症の方の心に寄り添い、適切なケアを提供するための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| パーソン・センタード・ケア | ぱーそん・せんたーど・けあ | 認知症の人を一人の「人」として尊重し、その人の視点に立ったケア。 | 「パーソン・センタード・ケアの理念に基づき、ご本人の気持ちを大切にします」 |
| バリデーション | ばりでーしょん | 認知症の方の言動を否定せず、その世界観を受け入れる技法。 | 「バリデーションの技法で、不安な気持ちに寄り添います」 |
| リアリティ・オリエンテーション | りありてぃ・おりえんてーしょん | 現実の時間、場所、人を繰り返し伝え、見当識を保つ技法。 | 「朝の挨拶で、今日の日付と天気を伝えるリアリティ・オリエンテーションを行います」 |
| 回想法 | かいそうほう | 昔の思い出を語ってもらうことで、心の安定を図る技法。 | 「古い写真を見ながら、回想法を実施しました」 |
| 徘徊 | はいかい | 目的なく歩き回ること。 | 「夜間の徘徊があるため、転倒に注意が必要です」 |
| 帰宅願望 | きたくがんぼう | 「家に帰りたい」という強い訴え。 | 「夕方になると、帰宅願望が強くなる傾向があります」 |
| 物盗られ妄想 | ものとられもうそう | 「誰かに物を盗まれた」と思い込むこと。 | 「物盗られ妄想があり、財布がないと訴えられます」 |
| 失認 | しつにん | 感覚器官は正常だが、対象が何かわからなくなること。 | 「視覚失認があり、鏡に映った自分を認識できません」 |
| 失行 | しっこう | 運動機能は正常だが、目的に沿った動作ができなくなること。 | 「着衣失行があり、服の着方がわからなくなっています」 |
| 失語 | しつご | 言葉を話す、理解する能力が損なわれること。 | 「運動性失語があり、言いたいことが言葉にできません」 |
2-4. 【制度・サービスで使う言葉】(10選)
介護保険制度や、様々なサービスを理解するための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 要介護度 | ようかいごど | 介護の必要度を示す7段階の区分(要支援1・2、要介護1〜5)。 | 「〇〇さんは、要介護度3です」 |
| ケアマネージャー | けあまねーじゃー | 介護支援専門員。ケアプランを作成し、サービスを調整する専門職。 | 「ケアマネージャーと連携して、サービス内容を見直します」 |
| 地域包括支援センター | ちいきほうかつしえんせんたー | 高齢者の総合相談窓口。 | 「地域包括支援センターに、介護の相談をしてみましょう」 |
| 居宅サービス | きょたくさーびす | 自宅で受ける介護サービス(訪問介護、デイサービスなど)。 | 「居宅サービスを利用して、在宅生活を継続されています」 |
| 施設サービス | しせつさーびす | 施設に入所して受ける介護サービス(特養、老健など)。 | 「在宅が難しくなり、施設サービスへの移行を検討しています」 |
| デイサービス | でいさーびす | 日帰りで通う介護サービス。 | 「週に3回、デイサービスを利用されています」 |
| ショートステイ | しょーとすてい | 短期間、施設に宿泊する介護サービス。 | 「ご家族の休息のため、ショートステイを利用します」 |
| 訪問介護 | ほうもんかいご | ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護を提供するサービス。 | 「訪問介護で、週に2回、入浴介助を受けています」 |
| 訪問看護 | ほうもんかんご | 看護師が自宅を訪問し、医療的なケアを提供するサービス。 | 「訪問看護で、褥瘡の処置を受けています」 |
| リハビリテーション | りはびりてーしょん | 心身の機能を回復させるための訓練。 | 「退院後は、訪問リハビリテーションを利用します」 |
2-5. 【看取り・終末期ケアで使う言葉】(10選)
人生の最期を支えるための、大切な言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ターミナルケア | たーみなるけあ | 終末期のケア。 | 「ターミナルケアに入り、苦痛の緩和を最優先にします」 |
| 看取り | みとり | 人生の最期を、そばで見守り支えること。 | 「施設での看取りを希望されています」 |
| 緩和ケア | かんわけあ | 苦痛を和らげ、QOLを保つためのケア。 | 「痛みのコントロールのため、緩和ケアを行います」 |
| アドバンス・ケア・プランニング(ACP) | あどばんす・けあ・ぷらんにんぐ | 人生の最終段階における医療・ケアについて、本人・家族・医療者が話し合うプロセス。 | 「ACPを通じて、ご本人の意思を確認します」 |
| 人生会議 | じんせいかいぎ | ACPの愛称。 | 「人生会議で、最期をどう過ごしたいか話し合いましょう」 |
| リビングウィル | りびんぐうぃる | 終末期医療に関する本人の意思表明書。 | 「リビングウィルに、延命治療を望まないと記されています」 |
| DNR | でぃーえぬあーる | Do Not Resuscitateの略。心肺蘇生を行わないこと。 | 「ご家族の希望で、DNRとなっています」 |
| グリーフケア | ぐりーふけあ | 大切な人を亡くした方への心のケア。 | 「ご家族へのグリーフケアも、私たちの大切な役割です」 |
| エンゼルケア | えんぜるけあ | 亡くなった方の体を清潔にし、整える死後のケア。 | 「エンゼルケアを丁寧に行い、最期のお別れをします」 |
| 尊厳死 | そんげんし | 延命治療を行わず、自然な形で最期を迎えること。 | 「ご本人の意思を尊重し、尊厳死を選択されました」 |
第3章:【リーダー向け】管理者・指導者のための専門50語
現場のリーダーを任されている方、将来的に管理者や教育担当者になりたい方のための、より高度で専門的な視点の用語50選をご紹介します。
3-1. マネジメント・運営管理(10選)
チームや施設を円滑に動かすための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| PDCAサイクル | ぴーでぃーしーえーさいくる | Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)を繰り返す品質管理手法。 | 「前回の業務改善案について、PDCAサイクルを回して効果を検証しましょう」 |
| 5S活動 | ごえすかつどう | 整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)の5つの頭文字。職場環境を整える活動。 | 「備品倉庫の5S活動を徹底し、探す時間を削減します」 |
| 業務改善 | ぎょうむかいぜん | 仕事の手順や方法を見直し、効率や質を高めること。 | 「申し送りの時間を短縮するため、業務改善の提案を募集します」 |
| BCP | びーしーぴー | 事業継続計画。災害など緊急時に、最低限のサービスを維持するための計画。 | 「BCPに基づき、年に一度は防災訓練を実施しています」 |
| KPI | けーぴーあい | 重要業績評価指標。目標達成度を測るための具体的な数値指標。 | 「今年度のKPIとして、ヒヤリハット報告件数20%増を掲げます」 |
| SWOT分析 | すうぉっとぶんせき | 強み(S)・弱み(W)・機会(O)・脅威(T)を分析し、戦略を立てる手法。 | 「自施設のSWOT分析を行い、今後の事業戦略を考えましょう」 |
| ステークホルダー | すてーくほるだー | 利害関係者(利用者、家族、職員、地域住民、行政など)。 | 「地域のステークホルダーと良好な関係を築くことが、安定した運営に繋がる」 |
| アライアンス | あらいあんす | 企業や組織間の連携、提携。 | 「地域の医療法人とアライアンスを組み、医療連携を強化する」 |
| 稼働率 | かどうりつ | 定員に対する実際の利用者数の割合。施設の収益に直結する指標。 | 「今月の入所施設の稼働率は95%でした」 |
| 労務管理 | ろうむかんり | 職員の労働時間、休日、給与、福利厚生などを適切に管理すること。 | 「職員が長く働けるよう、適切な労務管理が求められる」 |
3-2. 法令遵守・コンプライアンス(10選)
組織を守り、適切なサービスを提供するための法律や決まり事です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 実地指導 | じっちしどう | 行政が介護事業所を訪れ、運営が法令通り適切に行われているか確認すること。 | 「来月、実地指導が入るので、関連書類を準備してください」 |
| 運営指導 | うんえいしどう | 実地指導の旧称。 | 「前回の運営指導での指摘事項は、すべて改善済みです」 |
| 身体拘束廃止 | しんたいこうそくはいし | 利用者の身体の自由を奪う行為(縛る、閉じ込める等)を原則禁止すること。 | 「身体拘束廃止の理念を全職員が理解し、代替ケアを検討する」 |
| 介護保険法 | かいごほけんほう | 介護保険制度を定めた法律。すべてのサービスの根拠となる。 | 「介護保険法に基づき、利用者の自立支援をサービスの基本とします」 |
| 個人情報保護法 | こじんじょうほうほごほう | 個人のプライバシーに関わる情報の取り扱いを定めた法律。 | 「個人情報保護法を遵守し、利用者情報の管理を徹底する」 |
| 虐待防止法 | ぎゃくたいぼうしほう | 高齢者への虐待を禁止し、発見時の通報義務を定めた法律。 | 「虐待防止法に基づき、虐待の兆候を見逃さない体制を作ります」 |
| コンプライアンス | こんぷらいあんす | 法令遵守。法律や社会的ルールを守ること。 | 「コンプライアンスを徹底し、社会から信頼される施設を目指します」 |
| 内部監査 | ないぶかんさ | 組織内で、業務が適切に行われているか自主的にチェックすること。 | 「年に一度、内部監査を実施し、問題点を洗い出します」 |
| リスクマネジメント | りすくまねじめんと | 事故やトラブルを予測し、未然に防ぐための管理手法。 | 「リスクマネジメントの視点で、転倒事故の要因を分析します」 |
| 苦情対応 | くじょうたいおう | 利用者や家族からの苦情を適切に受け止め、改善に繋げること。 | 「苦情対応マニュアルに沿って、誠実に対応します」 |
3-3. 人材育成・教育(10選)
後輩を育て、チーム全体のスキルを向上させるための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| OJT | おーじぇいてぃー | On the Job Trainingの略。実際の業務を通じて行う教育。 | 「新人には、OJTで移乗介助の技術を教えます」 |
| Off-JT | おふじぇいてぃー | Off the Job Trainingの略。業務を離れて行う研修や勉強会。 | 「外部講師を招いて、Off-JTを実施します」 |
| プリセプター制度 | ぷりせぷたーせいど | 新人職員に先輩職員がマンツーマンで指導する制度。 | 「プリセプター制度で、新人の不安を軽減します」 |
| メンター制度 | めんたーせいど | 経験豊富な先輩が、後輩の相談役となる制度。 | 「メンター制度で、キャリアの悩みを相談できます」 |
| スーパービジョン | すーぱーびじょん | 経験豊富な指導者が、職員の専門性向上を支援すること。 | 「月に一度、スーパービジョンを受けて、ケアを振り返ります」 |
| キャリアパス | きゃりあぱす | 職員が成長していく道筋や、昇進・昇格の仕組み。 | 「明確なキャリアパスを示すことで、職員のモチベーションを高めます」 |
| コンピテンシー | こんぴてんしー | 高い成果を上げる人に共通する行動特性。 | 「リーダーに求められるコンピテンシーを明確にします」 |
| フィードバック | ふぃーどばっく | 相手の行動や成果に対して、評価や改善点を伝えること。 | 「定期的にフィードバックを行い、成長を支援します」 |
| エンパワメント | えんぱわめんと | 職員が自ら考え、行動できるよう力を引き出すこと。 | 「エンパワメントの視点で、職員の主体性を育てます」 |
| チームビルディング | ちーむびるでぃんぐ | チームの結束力を高め、協力し合える関係を築くこと。 | 「レクリエーションを通じて、チームビルディングを図ります」 |
3-4. リスク管理・安全対策(10選)
利用者さんと職員の安全を守るための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| リスクアセスメント | りすくあせすめんと | 危険を予測し、その大きさを評価すること。 | 「転倒のリスクアセスメントを行い、対策を立てます」 |
| 事故報告書 | じこほうこくしょ | 実際に起きた事故の内容や対応を記録する書類。 | 「転倒事故が発生したので、事故報告書を作成します」 |
| 再発防止策 | さいはつぼうしさく | 同じ事故が起きないようにするための対策。 | 「再発防止策として、夜間の見守り体制を強化します」 |
| 感染症対策 | かんせんしょうたいさく | 感染症の発生や拡大を防ぐための対策。 | 「インフルエンザの感染症対策として、手洗いとマスク着用を徹底します」 |
| 標準予防策(スタンダードプリコーション) | ひょうじゅんよぼうさく | すべての人の血液・体液を感染の可能性があるものとして扱う感染対策の基本。 | 「標準予防策に基づき、手袋とエプロンを着用します」 |
| 災害対策 | さいがいたいさく | 地震や火災などの災害に備えた対策。 | 「災害対策マニュアルを見直し、避難訓練を実施します」 |
| 防災訓練 | ぼうさいくんれん | 災害時の避難や対応を練習すること。 | 「年に2回、防災訓練を実施しています」 |
| 安全管理委員会 | あんぜんかんりいいんかい | 施設の安全対策を検討・推進する委員会。 | 「安全管理委員会で、事故の傾向を分析します」 |
| 医療安全 | いりょうあんぜん | 医療行為における事故を防ぐための取り組み。 | 「医療安全の観点から、薬の誤配を防ぐダブルチェックを行います」 |
| 食品衛生 | しょくひんえいせい | 食中毒を防ぐための衛生管理。 | 「食品衛生管理を徹底し、安全な食事を提供します」 |
3-5. 経営・財務(10選)
施設の持続的な運営を支えるための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| 介護報酬 | かいごほうしゅう | 介護サービスを提供した対価として、事業所が受け取る報酬。 | 「介護報酬の改定により、収益構造が変わります」 |
| 加算 | かさん | 基本の介護報酬に上乗せされる報酬。 | 「看護体制加算を算定するため、看護師の配置を増やします」 |
| 減算 | げんさん | 基準を満たさない場合に、介護報酬が減額されること。 | 「人員基準を満たさないと、減算の対象になります」 |
| 単位数 | たんいすう | 介護報酬を計算するための基準となる数値。 | 「訪問介護の単位数は、サービス内容によって異なります」 |
| 収支 | しゅうし | 収入と支出。 | 「今月の収支を確認し、経営状況を把握します」 |
| 利益率 | りえきりつ | 収入に対する利益の割合。 | 「利益率を向上させるため、業務効率化を進めます」 |
| 予算管理 | よさんかんり | 計画的に予算を立て、支出を管理すること。 | 「適切な予算管理で、無駄な支出を削減します」 |
| コスト削減 | こすとさくげん | 費用を減らすこと。 | 「業務改善によるコスト削減を目指します」 |
| 人件費 | じんけんひ | 職員の給与や福利厚生にかかる費用。 | 「人件費が経営を圧迫しないよう、適正な人員配置を行います」 |
| 稼働率向上 | かどうりつこうじょう | 定員に対する利用者数の割合を高めること。 | 「稼働率向上のため、地域への広報活動を強化します」 |
3-6. ICT・DX(10選)
介護現場のIT化・デジタル化を推進するための言葉です。
| 用語 | よみがな | 意味 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ICT | あいしーてぃー | Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 | 「ICTを活用して、記録業務を効率化します」 |
| DX | でぃーえっくす | Digital Transformationの略。デジタル技術で業務やサービスを変革すること。 | 「介護現場のDXを推進し、職員の負担を軽減します」 |
| 介護ロボット | かいごろぼっと | 介護を支援するロボット(移乗支援、見守りセンサーなど)。 | 「介護ロボットを導入し、腰痛予防と業務効率化を図ります」 |
| 見守りセンサー | みまもりせんさー | 利用者の動きを感知し、転倒や離床を知らせる機器。 | 「見守りセンサーで、夜間の安全を確保します」 |
| インカム | いんかむ | 職員同士が離れた場所でも会話できる無線通信機器。 | 「インカムを導入し、迅速な情報共有を実現します」 |
| タブレット端末 | たぶれっとたんまつ | 記録や情報確認に使う携帯型コンピューター。 | 「タブレット端末で、その場で記録を入力できます」 |
| クラウド | くらうど | インターネット上にデータを保存・共有する仕組み。 | 「クラウドシステムで、どこからでも記録を確認できます」 |
| AI | えーあい | 人工知能。データを学習し、判断や予測を行う技術。 | 「AIを活用して、転倒リスクを予測します」 |
| ペーパーレス化 | ぺーぱーれすか | 紙の書類を減らし、電子化すること。 | 「ペーパーレス化で、書類管理の手間を削減します」 |
| 業務支援システム | ぎょうむしえんしすてむ | 介護記録や請求業務を効率化するソフトウェア。 | 「業務支援システムを導入し、記録時間を半減させました」 |
第4章:【場面別】逆引き介護用語辞典
「こんな時、何て言えばいいんだろう?」という疑問を解決するための、場面別の逆引き辞典です。
4-1. 食事の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| 食事を手伝う | 食事介助 |
| 食べ物を飲み込む | 嚥下 |
| 食べ物が気管に入る | 誤嚥 |
| むせる | むせ込み |
| 食事を全部食べた | 完食 |
| 食事を半分食べた | 半量摂取 |
| 食事をほとんど食べなかった | 摂取不良 |
| 食事の形を変える | 食形態の変更(刻み食、ミキサー食など) |
| 食事の前の体操 | 嚥下体操 |
| 口から食事ができない | 経管栄養 |
4-2. 排泄の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| トイレに行く | トイレ誘導 |
| おむつを交換する | おむつ交換 |
| 尿が出ない | 尿閉 |
| 便が出ない | 便秘 |
| 下痢をしている | 下痢 |
| 尿の管を入れている | バルーンカテーテル |
| 人工肛門 | ストーマ |
4-3. 入浴の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| お風呂に入る | 入浴 |
| 体を拭く | 清拭 |
| 足だけ洗う | 足浴 |
| 手だけ洗う | 手浴 |
| 部分的に洗う | 部分浴 |
4-4. 移動の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| ベッドから車椅子に移る | 移乗 |
| ベッドから起きる | 離床 |
| ベッドに横になる | 臥床 |
| 体の向きを変える | 体位交換 |
| 歩く | 歩行 |
| 車椅子を押す | 車椅子介助 |
| 歩行を手伝う | 歩行介助 |
4-5. 体調観察の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| 体温・血圧を測る | バイタルサイン測定 |
| 熱がある | 発熱 |
| 顔色が悪い | 顔色不良 |
| むくんでいる | 浮腫 |
| 床ずれができている | 褥瘡 |
| 皮膚が赤い | 発赤 |
| かゆがっている | 掻痒感 |
| 眠そう | 傾眠 |
| 落ち着かない | 不穏 |
4-6. 認知症ケアの場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| 歩き回っている | 徘徊 |
| 家に帰りたいと言う | 帰宅願望 |
| 物を盗まれたと言う | 物盗られ妄想 |
| 時間や場所がわからない | 見当識障害 |
| 昔の話をする | 回想法 |
| その人の世界観を受け入れる | バリデーション |
| その人を中心にケアする | パーソン・センタード・ケア |
4-7. 事故・リスク管理の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| 転びそうになった | ヒヤリハット |
| 実際に転んだ | 転倒事故 |
| 薬を間違えそうになった | インシデント |
| 事故を防ぐ | リスクマネジメント |
| 危険を予測する | リスクアセスメント |
| 同じ事故を防ぐ | 再発防止策 |
4-8. チーム連携の場面
| 場面 | 使う用語 |
|---|---|
| 情報を引き継ぐ | 申し送り |
| ケアについて話し合う | カンファレンス |
| 情報を集めて分析する | アセスメント |
| 効果を観察する | モニタリング |
| 様々な職種が協力する | 多職種連携 |
| ケアの計画書 | ケアプラン |
第5章:【無料ツール】AIでいつでもどこでも専門用語を学習
記事を読んだだけでは、知識はなかなか身につきません。
ここでは、この記事で学んだ150個の専門用語を、もっと効率的に、もっと楽しく復習するための無料学習ツールをご紹介します。
5-1. 介護専門用語マスター道場
通勤時間や休憩中など、ちょっとしたスキマ時間にスマホやPCで手軽に挑戦できる、オリジナル学習ツール「介護専門用語マスター道場」を開発しました!
【このツールの3つの特徴】
- 2つのモードで楽しく学べる!
- じっくり自分のペースで復習できる「単語カードモード」
- ゲーム感覚で知識を確認できる「四択クイズモード」
- 苦手な分野を集中特訓できる!
- 「身体介助」や「状態観察」など、学びたい分野を絞って学習できます。
- 登録不要&完全無料でいつでも使える!
- インストールや会員登録は一切不要。このページですぐに学習を始められます。
このツールで繰り返しアウトプットして、「わかる」を「できる」に変えていきましょうね!
5-2. AI学習アシスタント(無料ツールはこちら!)
さらに、ChatGPTやGeminiなどのAIツールを活用すれば、いつでもどこでも専門用語を学習できます。
新人・外国人向け|まずは覚えるべき必須50語【無料学習AIツール】
介護専門用語マスター道場
単語カードとクイズで、必須用語をマスターしよう!
用語
クリックして意味を見る
意味
例文
問題
スコア: 0
結果発表!
0 / 0
チームで活躍するための応用50語【無料学習AIツール】
介護専門用語マスター道場
【中級編】
用語
クリックして意味を見る
意味
例文
問題
スコア: 0
結果発表!
0 / 0
リーダー向け|管理者・指導者のための専門50語【無料学習AIツール】
介護専門用語マスター道場
【上級編】
用語
クリックして意味を見る
意味
例文
問題
スコア: 0
結果発表!
0 / 0
5-3. PDFダウンロード
この記事で紹介した150個の専門用語を、PDFにまとめて無料配布しています。
印刷してポケットに入れたり、デスクの前に貼ったりして、日々の学習にお役立てください。
新人・外国人向け|まずは覚えるべき必須50語【無料PDF配布】
スキルアップしたい中堅向け|チームで活躍するための応用50語【無料PDF配布】
リーダー向け|管理者・指導者のための専門50語【無料PDF配布】
明日からできる!専門用語マスターへの3ステップ
ステップ1:インプットとアウトプットを繰り返す
まずは覚えること(インプット)が大切ですが、それと同じくらい「使ってみる」(アウトプット)が重要です。
今日覚えた言葉を、意識して記録で使ってみる。
同僚との会話で「〇〇さんのケアって、一部介助でしたっけ?」と確認してみる。
この繰り返しが、知識を定着させる一番の近道です。
ステップ2:自分の「単語帳」を作る
アナログなノートでも、スマホのメモアプリでも構いません。
わからない言葉が出てきたら、その場ですぐにメモする習慣をつけましょう。
後で意味を調べて書き足せば、あなただけのオリジナル単語帳が完成します。
私のオススメは、写真も貼れるメモアプリです。言葉と画像をセットにすると、記憶に残りやすいですよ。
ステップ3:「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」を心に刻む
これが一番大切かもしれません。わからないことを、わからないままにしない。
その場で聞けなくても、後で必ず誰かに聞く。
「こんなことも知らないのかって思われたらどうしよう…」という不安より、「知ったかぶりをして、利用者さんを危険に晒すこと」の方が何百倍も怖いことです。
あなたのその一言の勇気が、あなたと利用者さんを守りますから。
おわりに:言葉を磨き、ケアを磨く
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。
新しい環境、それも介護という、人の生活と命に深く関わる仕事へ一歩を踏み出したあなたは、日本人でも、外国人でも、本当に素晴らしい「チャレンジャー」です。
慣れない言葉、覚えるべき知識の多さに、くじけそうになる日もあると思います。私自身も、数え切れないほどの失敗を重ねてきました。でも、その一つ一つの失敗が、言葉の重みと正確に伝えることの大切さを教えてくれました。
言葉の壁は、決してあなたを阻むためだけにあるのではありません。その壁を乗り越えようと努力する過程で、あなたは日本の介護の心、相手を思いやる気持ちをより深く理解できるようになるはずですから。
専門用語を学ぶことは、ただの暗記作業ではありません。
あなたの介護士としてのキャリアを支える、最も重要で最も確実な土台作りです。
一つひとつの言葉を大切に学び、あなたのケアを確かなものにしていきましょうね。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、明日からの学習への「お守り」のような存在になれたなら嬉しいです。あなたの挑戦を、心から応援していますね!
あわせて読みたい記事
✏️ 毎日の記録・申し送りを「時短」したい方へ
「やさしい日本語」と一緒に使うと効果抜群。Excelでそのまま使えるテンプレートです。


💬 利用者さんともっと「心通う会話」がしたい方へ
業務的な指示だけでなく、相手の心が動く「魔法の言葉」や「感謝の伝え方」を集めました。
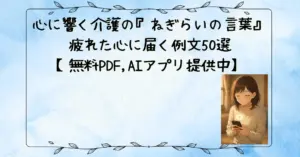
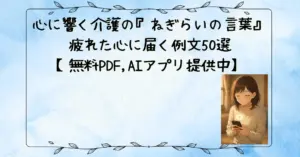
🤖 AIを使って「自分だけのマニュアル」を作りたい方へ
今回のChatGPT活用法をさらに深掘り。現場ですぐ使えるフレーズやプロンプトをまとめたPDF付き記事です。


追伸:もう少しだけ、お付き合いください
ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!
この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。
▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。
▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。
もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!
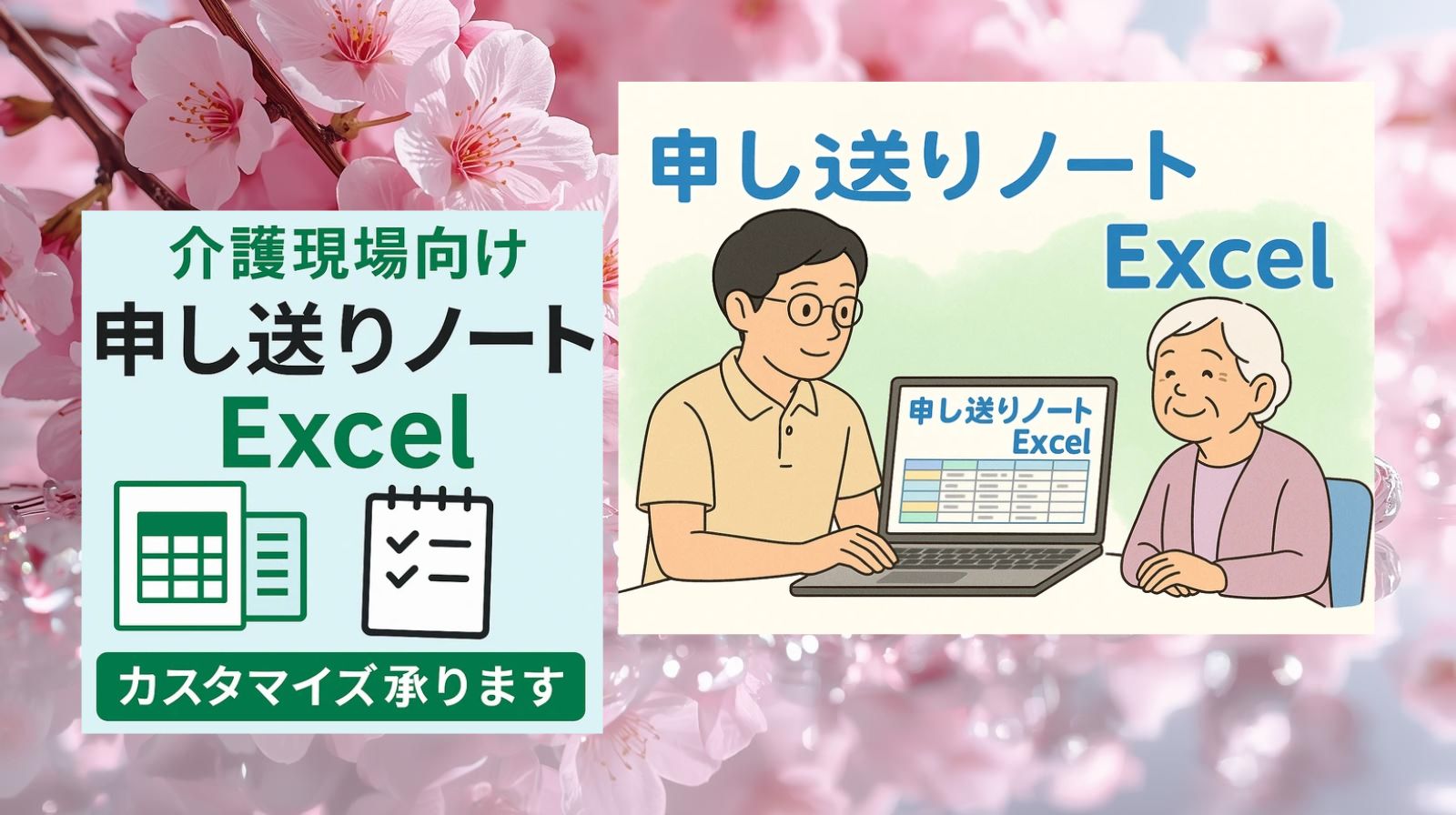

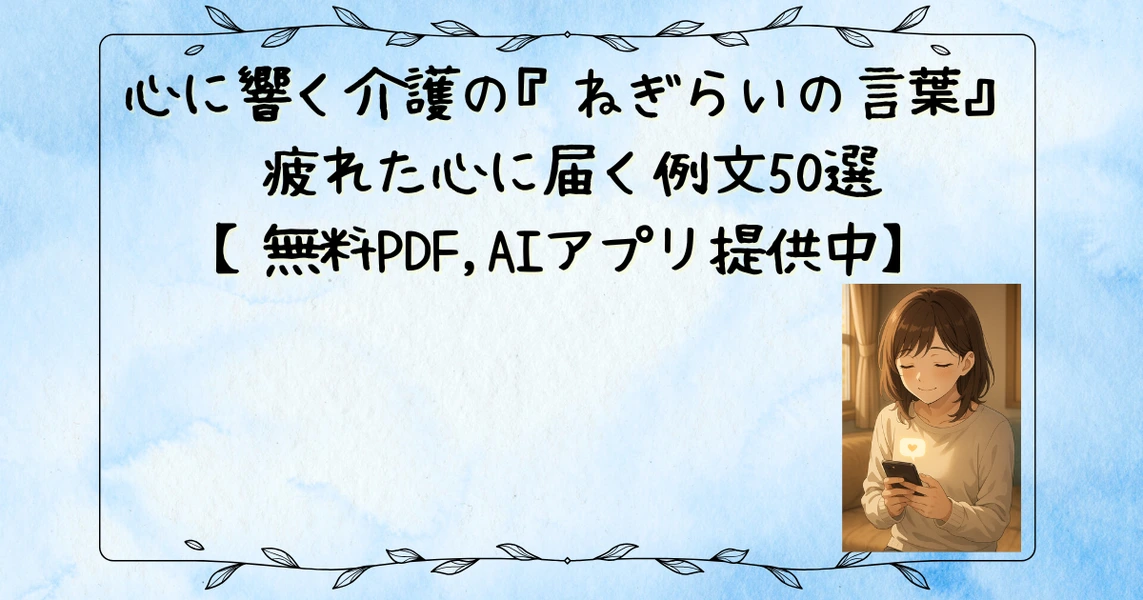


コメント